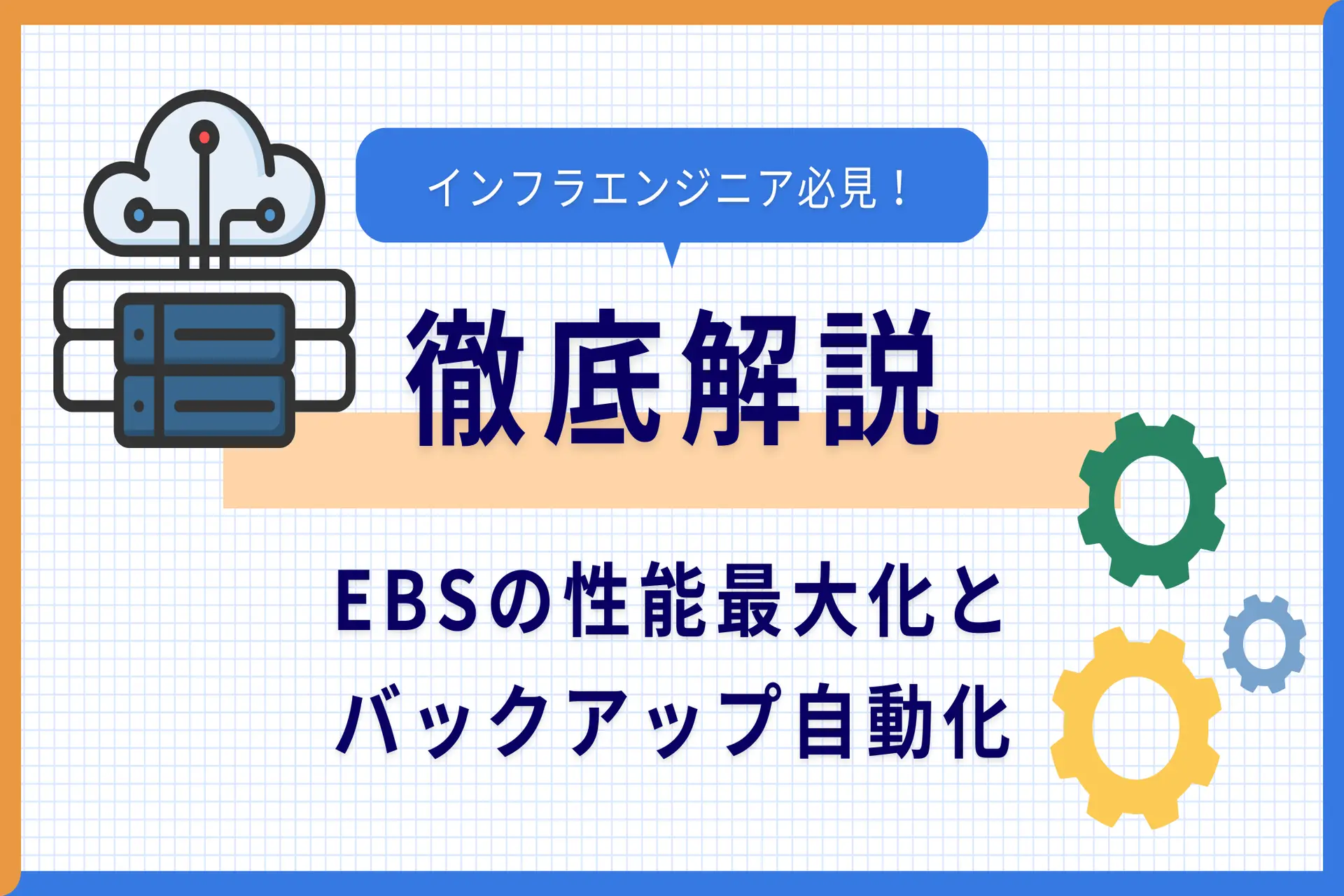DXが進まない本当の理由とは?企業が直面するDXの問題点と解決策
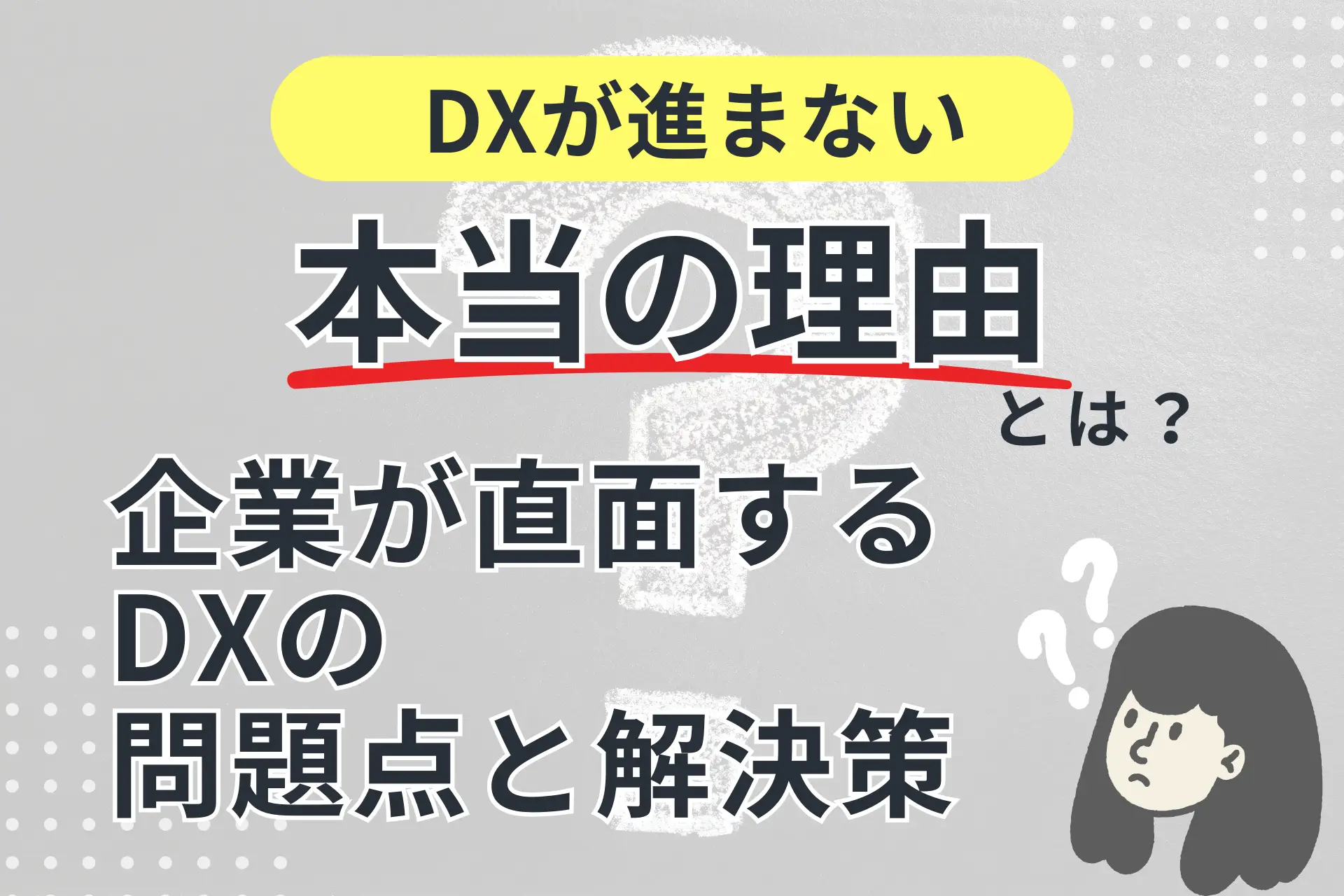
目次
1. なぜ今、DXが重要なのか
近年、多くの企業が「DX(デジタルトランスフォーメーション)」に注目するようになりました。
これは単なるデジタル技術の導入ではありません。
デジタルを活用して、企業の仕組みやビジネスモデルそのものを変え、他社との差別化を進めながら持続的に成長しようという動きです。
特に近年は、デジタル技術の進化とともに市場環境の変化も激しく、商品やサービスがすぐに陳腐化する時代です。
このような中で変化に適応できない企業は、ゆるやかに競争から脱落していくリスクを抱えています。
ここでは、DXがなぜ重要なのか、日本企業が抱える背景や課題について解説します。
1-1.DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義
そもそもDXとは、「デジタル技術を使って、企業や組織が仕組みややり方を抜本的に進化させること」です。
「紙をデジタル資料に変える」「ハンコを廃止する」などの作業はDXではなく、“デジタイゼーション”(データ化)や“デジタライゼーション”(業務のデジタル化)と呼ばれる段階にすぎません。
本質的なDXは、こうしたデジタル化を出発点として、業務フローの見直しや組織の再設計を通じ、企業の在り方そのものを変えていくことが目的です。
1-2.競争力と新価値創出の関係
企業がDXに取り組む最大の理由は、「競争力の維持・強化」と「新しい価値の創出」です。
市場や顧客のニーズが多様化し、従来のやり方では対応しきれなくなった今、デジタル技術を活かしてビジネスモデルやユーザー体験を改善していく必要があります。
AI(人工知能)を使って需要予測を精緻化したり、IoT(モノのインターネット)によって製品の故障を予測したりすることで、今まで得られなかった価値を生むことも可能です。
競争に耐えうる仕組みは進化しており、それに適応することが求められているのです。
1-3.日本企業の現状と課題意識
日本企業では、DXの重要性を理解してはいるものの、実際の取り組みがうまく進んでいないケースが多く見られます。
特に、情報システム部やDX推進室で旗を振る立場にある方の中には、「経営層の理解が得られない」「現場の非協力に苦労している」「古い基幹システムが壁になっている」といった課題に直面している方が少なくありません。
このような課題を乗り越えるためには、なぜDXが停滞するのか、その本質的な原因を正しく理解し、解決に取り組むことが不可欠です。
2. DX推進が進まない企業に共通する3つの問題点
DXに対する関心は高まっている一方で、具体的な成果につながらない企業が多いのが実情です。
現場の業務フローが属人化・アナログ化している企業では、ITツールの導入が思うように進みません。
業務が人に依存しており、明確な手順書も存在しないため、外部ツールを入れても結局使いこなせず、定着しないという状況が多く見られます。
こうした課題は中堅製造業に多く見られますが、サービス業や小売業(宿泊業やスーパーマーケット)など、他の業種でも共通して見られる傾向です。
業務の可視化や標準化ができていないと、どの業種においてもDXのスタートラインに立つことすら難しくなってしまいます。
2-1.経営陣の危機意識・ビジョン不足
DXは経営そのものに関わる変革です。
ところが多くの企業では、経営陣が「なんとなく必要そうだから」というレベルで捉えていることが少なくありません。
経営トップ自らが、デジタル化によって何を目指すのかというビジョンを持たないままプロジェクトを任せてしまうと、組織全体の動きがバラバラになり、推進している実感も得にくくなります。
特に中堅製造業では、「今までこれでやってきた」という成功体験が強く、変化への踏み出しを躊躇する傾向が顕著です。
2-2.現場とのギャップとコミュニケーション不全
情報システム部門がいくらデジタル化を進めようとしても、現場がその背景や目的を理解していなければ意味がありません。
しかも、現場と推進部門が使っている言葉が違ったり、業務の見方が異なることで、互いに伝えたいことが伝わらず誤解が生まれやすくなります。
こうしたコミュニケーションの分断が進むと、「DX=余計な仕事を増やすもの」と捉えられ、現場の協力が得られなくなるのです。
2-3.システムの老朽化とサイロ化したIT基盤
多くの日本企業のITシステムは、10〜20年前の基幹系システムが中核に据えられています。
こうしたシステムは長年の運用で部署ごとに独立しており、情報のやり取りが困難になっています(これを「サイロ化」といいます)。
その結果、全社的な最適化やスピーディーな意思決定が難しく、変化への柔軟性を欠いたまま運用されてしまうのです。
デジタル技術を取り入れても、土台が古ければその効果は半減してしまいます。
3. 課題①:経営のコミットメント不足
DX推進が進まない理由の根本にあるのは、「経営の本気度の欠如」です。
組織を変えるという大きな目標には、社内のいたるところで摩擦やコストが伴います。
それでも進めなければならない理由を、経営層自身が腹落ちしていないと、改革は決して成功しません。
3-1.DXの目的が曖昧なままの導入事例
「とりあえず流行に乗ってAIを導入してみた」「アプリを作ったが使われていない」──このような事例が実際に多く見られます。
こうした失敗事例に共通しているのは、明確な目的が設定されていないことです。
「何のためにデジタルを使って改革するのか」が定まらないまま進めてしまうと、プロジェクトは迷走し、現場には混乱と不信感だけが残ってしまいます。
DXはあくまで手段であり、企業が目指す将来像や課題解決のための道筋が明確になってこそ、価値を発揮するという理解が極めて重要です。
3-2.推進体制が整っていないケース
またもう一つの問題は、DXを進める体制が整っていないことです。
役職だけ「CDXO(チーフ・デジタル・トランスフォーメーション・オフィサー)」のような肩書を新設しても、彼や彼女を支える仕組みや各部門との連携がなければ有名無実化してしまいます。
現場では「単なる形だけの改革」と捉えられ、協力意識も薄れていきます。
DXを本気で成功させるには、トップから現場までの連携と、本気で変わるという姿勢の共有が何よりも重要です。
4. 課題②:社員の理解不足・スキルギャップ
DXの推進には、経営層の理解と同時に、現場社員の理解と協力が欠かせません。
しかし、実際には社員がDXの本質を理解しておらず、変革への不安や抵抗感から非協力的になるケースが多く見られます。
このような状況が生まれる背景には、DXに必要な知識やスキルのギャップがあり、それを埋める教育体制が不足しているという課題があります。
4-1.DX人材の定義と市場ニーズ
まず、DX推進において求められる「DX人材」とはどういった人のことを指すのでしょうか。
一般に、デジタル技術だけを扱えるIT専⾨職を想像されるかもしれませんが、それだけではありません。
ビジネスモデルを理解し、業務とITの橋渡しができる人。
新しいアイデアを企画し、データを活⽤した意思決定ができる人。
あるいは、変革に向けたプロジェクトを円滑にまとめられるマネジメントスキルを持つ人もDX人材です。
特に中堅製造業のような業界では、現場の作業プロセスに深く関わりながら改革を促す「業務×IT」型人材へのニーズが高まっています。
4-2.社内教育の不足と育成体制の欠如
DX人材の需要が高まる一方で、多くの企業で課題となっているのが「社内育成の不足」です。
外部採用だけに頼るのでは限界があります。
実際、多くの企業では現場社員がデジタル技術に対して拒否反応を示す傾向が強く、「勉強する時間がない」「自分には関係ない」と感じる社員も多いのが実情です。
その背景には、自社の社員に向けたDX教育・研修の機会が限定的であることが挙げられます。
社内で人材育成計画が明文化されておらず、体系立てて学べるプログラムを整備していない企業も多いのが実態です。
教育の第一歩は、「なぜ今これが必要なのか」を納得感を持って伝え、段階的にリスキル(新しいスキルの取得)を進められる体制をつくることです。
5. 課題③:レガシーシステムの壁
もう一つ、DX推進を物理的に阻害する要因が、古く複雑化したシステム、つまり「レガシーシステム」の存在です。
これは日本の多くの中堅企業に共通する構造的な壁の一つです。
5-1.サイロ化による情報共有の阻害
レガシーシステムの問題の多くは、「サイロ化(情報の孤立状態)」によって引き起こされます。
販売・在庫・製造・購買など各部門が独自に業務システムを持っており、別々のルールや仕様で管理されているケースです。
その結果、必要なデータが統合されず、手作業で情報を転記したり、複数のシステムを行き来したりと、非効率な作業が常態化しています。
また、全体の数値や状況をタイムリーに把握できないため、経営判断の精度にも大きな影響を及ぼします。
5-2.過剰なカスタマイズによる保守性の低下
多くの企業では過去に導入した基幹システムを、自社の業務に合わせて過度にカスタマイズしてきた歴史があります。
この「自社専用カスタマイズ」が行き過ぎると、以下のような問題が起こります。
社内の特定担当者でしか仕様がわからず、属人化が進む
バージョンアップや機能追加が困難になり、時代の変化に対応できない
新しいシステムや外部ツールとの連携ができない
結果的に、システムはどんどん「重く、融通が利かず、手が出せない」状態に陥ってしまいます。
DXを妨げる最も大きな要因の一つといえるでしょう。
6. 解決策:DX成功企業に学ぶアプローチ
ここまでに挙げた課題を乗り越えるために、多くの企業が模索しはじめたのが「成功企業に学ぶDXアプローチ」です。
ここでは、現場に根ざした実践方法として有効な3つの戦略をご紹介します。
6-1.トップダウン型とボトムアップ型の併用
DXの推進においては、「トップダウンでの明確な方向性の提示」と「現場からのボトムアップによるアイデア提案や課題発見」の両方が必要です。
トップダウン型では、経営層がビジョンを明確に打ち出し、必要な予算・人材配置を決定します。
一方で、現場の知見を軽視すると的外れな施策が生まれるため、実際の業務を担う社員からの提案やフィードバックループも不可欠です。
両者が連携しながら施策を磨いていくことで、プロジェクトの実効性と現実性が高まっていきます。
6-2.PoC(実証実験)から進める段階的導入
PoC とは「Proof of Concept(プルーフ・オブ・コンセプト)」の略称で、「構想や計画が現実に通用するかどうかをテストすること」を意味します。
一気に全社導入を目指すのではなく、小さな単位で試し、成果と課題を見極めながら段階的に改善・拡大していく方法です。
この手法のメリットは、リスクを最小限にしながらスピード感を持ってDXを進められる点にあります。
特に予算や体制が整っていない中堅企業にとっては、「まずは一部門で成果を出す」ことで社内に成功体験を広めやすくなります。
6-3.組織改革と人材育成の連動
DXは技術だけでなく、「人と制度」も同時に変革していくことが成功の鍵です。
従来の縦割り組織のままでは部門間の連携が難しく、プロジェクトが分断されてしまいます。
これを防ぐには、プロジェクト横断で連携できる柔軟な組織形態への転換が必要です。
同時に、人材育成も「現場での実践機会」と「座学による知識習得」をセットで提供し、社員が安心してスキルアップできる環境を整えることが求められます。
この“組織と人”の進化がともに進んでこそ、DXは本当に根付きます。
7. DX推進体制のつくり方
DXを推進するには、経営の覚悟や社員のスキルだけでなく、それを動かすための「実行体制」が必要です。
体制が曖昧なままだと、部門間での調整がうまくいかなかったり、責任の所在が不明確になったりして、プロジェクトが頓挫する可能性が高まります。
ここでは、組織としてDXを進める上で備えるべき3つの体制について紹介します。
7-1.CIO/CDXOなど専門人材の配置
DXに必要なのは、経営全体の視点でシステムやデジタル活用を見通せるリーダー的存在です。
代表的なのが以下のような役職です。
CIO(Chief Information Officer)
情報戦略の責任者CDXO(Chief Digital Transformation Officer)
デジタル変革の責任者
こうした専門職を新設することで、経営層と現場の橋渡しを担う人材が明確になります。
企業によっては、外部から登用するケースもありますが、ポイントは「デジタルだけに詳しいのではなく、ビジネス全体に関心が強い人」を充てることです。
なぜなら、DXは技術を使って経営の在り方を変える行為だからです。
もちろん、名前ばかりにならないようにミッションやサポート体制を企業として準備することは忘れずに行いましょう。
7-2.跨部門連携の仕組みづくり
DXは、すべての部署に影響するプロジェクトです。
そのため、組織間の「縦の壁」「横の壁」を取り払うことが欠かせません。
情報システム部・製造・品質管理・営業など、多様な視点の人材を集めた「DX推進会議」や「コーポレート横断チーム」を設置するケースがあります。
重要なのは、それぞれの部門が対等な立場で議論し、「全社の課題」として協働できる環境を整備することです。
一方通行の連絡ではなく、「課題→解決→検証」の一連の流れを共有しあえる文化づくりが成功の鍵です。
7-3.推進チームと現場の融合
DXは本社の推進チームだけで回すのではなく、必ず現場との連携・対話が求められます。
そのためには、現場の課題や業務に精通した人材をプロジェクトメンバーに参加させ、「机上の空論」で終わらせない仕組みを整える必要があります。
「現場の声をどう中に入れるか」その仕組みやフロー設計を徹底しましょう。
また、意見をくれた現場スタッフへのフィードバックも忘れてはいけません。
推進側だけで完結してしまうと、やがて現場は興味を失ってしまいます。
8. データドリブンな組織への転換
DXの最終的な目標のひとつは「データ活用を軸にした迅速で正確な判断ができる組織への変革」です。
いわゆる「データドリブン(データに基づく)」経営へのシフトです。
属人的なカンや経験だけでなく、数量的な根拠を活かす企業ほど、延いては収益性や成長率も高まる傾向にあります。
8-1.データ活用文化の醸成方法
「データを活用する」といっても、単に分析ツールを導入するだけでは意味がありません。
社内全体で、「重要な判断は数字に基づいて行う」という文化をつくる必要があります。
そのためには次のような工夫が効果的です。
日常的にダッシュボード(可視化ツール)を用いる
全員が共通のKPI(重要指標)にアクセスできるようにする
部門単位で小さな分析リテラシー教育を繰り返す
日本企業では、感覚や雰囲気で判断されてきた部分も多いため、まずは小さな現場業務から「数字で語る」習慣を浸透させることが重要です。
8-2.KPIとOKRの設定による成果指標の明確化
KPIとは「Key Performance Indicator(重要業績評価指標)」のことで、目標達成までの進捗を定量的に測るための指標です。
また、近年注目されている「OKR(Objectives and Key Results)」は、定性的な目標(O)と、それを測るための数値目標(KR)から構成され、柔軟性と挑戦性を兼ね備えたツールです。
目標と結果があいまいなDXプロジェクトではこれらを使って、進捗や達成感を「見える化」することが社内の納得感にもつながります。
9. DX推進を成功に導く外部パートナー活用
DXを社内の力だけで完結しようとするのは、非常に大きな負担になります。
経験豊富な外部パートナーの力をうまく借りることで、知見やスピードを補完できます。
安全かつ効果的に進めるために、以下の2つの観点から活用の方法を紹介します。
9-1.ベンダー・コンサルティングファームとの協働
システム開発やプロジェクトマネジメント、業務改善の知見を持った外部企業と連携することは非常に有効です。
コンサルティングファーム
構想策定や戦略立案をサポートITベンダー
システム構築やツール導入の実務を支援
自社の状況に応じて役割を切り分けると、効果的に進みます。
大切なのは「任せきりにしないこと」。自社の課題や目的を明確にしたうえで、対等なパートナーとして関わる意識が求められます。
9-2.テクノロジーパートナー選定のポイント
パートナーを選ぶ際には、以下の視点が重要です
自社の業種・業務プロセスへの理解があるか
現場の担当者に寄り添い、コミュニケーションが円滑に行えるか
成功事例が豊富で、改善提案や失敗回避策を持っているか
名の通った企業だから絶対に良い、とは限りません。
現場に合った提案をしてくれるパートナーをしっかりと見極める力が必要です。
10. 継続的改善が鍵となるDX成功戦略
DXは一度やって終わりではありません。
むしろ成功してからが本当のスタートです。
取り組むごとに新しい課題が見つかり、さらに次の改善策を考える ── こうした「継続的な変化対応力」こそが、DX本来の価値です。
成功企業が共通して持っている点や、今後DXをどう捉えていくべきかを振り返ります。
10-1.成功する企業の共通点
調査や事例を見ると、DXで成果を伸ばしている企業には共通項があります。
トップの本気度が高い
目的や目標が明確に定められている
技術だけでなく「人間」と「文化」の改革に取り組んでいる
小さな成功を積み重ねながら、組織に広げている
彼らは一足飛びで大きな改革を行ったわけではありません。
現場と並走し、失敗から学び、役割を明確にしながら着実に歩を進めています。
10-2.常に進化を求められるDXの捉え方
DXを「一つのプロジェクト」として終わらせてしまうのではなく、「自社を変えていく文化と風土を育てる持続的プロセス」と捉えることが重要です。
これまでのやり方を守れば守るほど、時代の変化には対応できなくなります。
逆に、多くの社員が「変化し続けることに前向きになる」組織をつくることが最大のゴールといえるでしょう。
ここに紹介した課題と対策が、DXの第一歩を踏み出す一助になれば幸いです。

 dx
dx