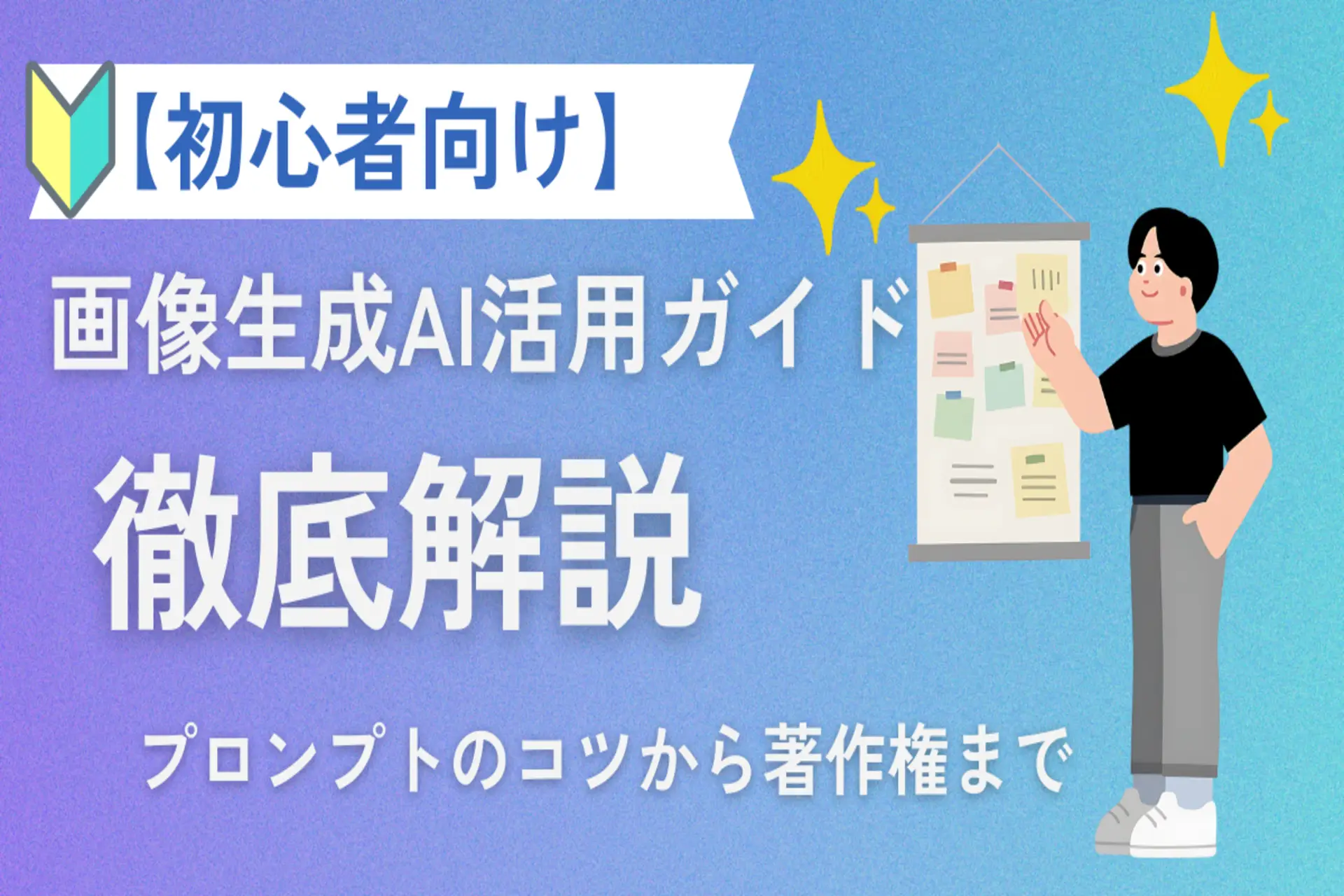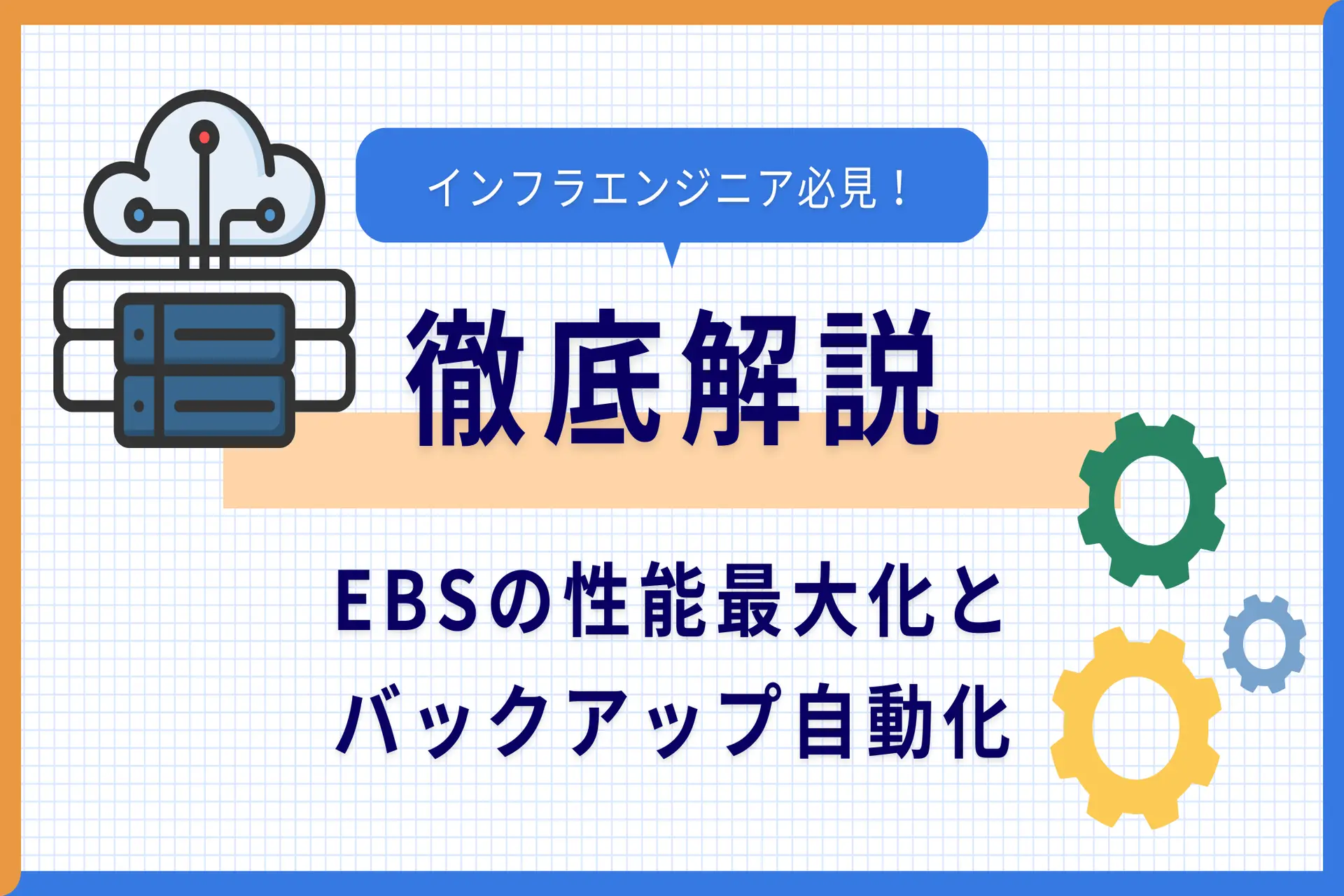【事例あり】農業DXできること|導入システム、効果を詳しく解説

目次
「最近『DX』という言葉を聞くけれど、農業ではどんなDXができる?」
「うちは中小規模の農家だが、DXは必要?」
そんな疑問を持っている方はいませんか?
「DX」とは「デジタルトランスフォーメーション」の略語で、「デジタル技術によって、商品やビジネスのあり方自体を変えること」を指します。
「農業DX」は、単に農業の現場にIT技術を導入するだけではなく、それによって課題を解決し、新しい農産物の市場を切り拓いたり、これまでになかったビジネスモデルを構築したりして消費者ニーズに応えて行くことだと考えればいいでしょう。
たとえば農業に導入できる技術とそれによるメリットには、以下のようなものが挙げられます。
【農業DXでできることとメリット】
・AIによる収穫予測→需要に則した供給
・農業機械の自動運転→人手不足の解消
・センシングによる適地適作→生産性向上
・ドローンによる薬剤散布や播種→作業の効率化
ただ、導入には課題もありますので、対策を講じなければなりません。
【農業DX実現への課題】
・デジタル技術に対応できない
・導入コストが必要
・法整備が不十分
そこでこの記事では、農業DXについて知っておきたいことをまとめました。
◎農業におけるDXとは
◎農業DXとスマート農業との違い
◎農業DXの事例
◎農林水産省が掲げる「農業DX構想」とは
◎農業DXでできることとメリット
◎農業DX実現への課題
◎農業DXが向いている農家とは
最後まで読めば、知りたかったことがわかるでしょう。
この記事で、あなたが農業のDX化に成功できるよう願っています。この記事は、デザインワン・ジャパン DX事業本部でDX支援に携わる泉川学が作成しました。
1.農業DXとは
そもそも農業におけるDX=「農業DX」とはどんなことを指すのでしょうか?
まずそのことから考えてみましょう。
1-1.農業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)とは?
「DX」とは「デジタルトランスフォーメーション」の略語で、「デジタル技術によって、商品やビジネスのあり方自体を変えること」を指します。
農林水産省では、農業や食関連産業の関係者が農業DXを進める際の指針である「農業DX構想 ~『農業×デジタル』で食と農の未来を切り拓く~(要約版)」という文書の中で、「農業DXにより実現を目指す姿」を以下のように述べています。
| 【農業DXにより実現を目指す姿】 農業や食関連産業に携わる方々がそれぞれの立場で思い描く「消費者ニーズを起点にしながら、デジタル技術を活用し、様々な矛盾を克服して価値を届けられる農業」 (例)・ 複数の自動走行トラクタの導入等により、少人数でも実行可能な超効率的な大規模生産を実現 ・ 消費者の購買データを元に需要の変化をつかみ、国内外の多様なニーズに機動的に対応した食料の生産を行い、供給することで、消費者の支持を獲得 ・ 作業の省力化や自動化に加え、AIの活用により予測の精度が上がることで、やる気のある農業者であれば、体力的にきつくなってきた高齢者であっても、まだ就農してからの期間が短い若手であっても、品質の高い農産物を安定的に生産できる経営を実現 ・ 地理的条件の不利な地域であっても、新技術の活用や土壌の特質に応じた適地適作を効率的に実行し、他の土地では生産することができない高い価値を持つ農産物として、適切な価格で販売 ・ 消費者のし好(「味」や「栄養」はもとより、食を通じて感じられる価値(安全・安心、健康・体質改善、一家団欒、エシカル消費など))にあった食品を、農業者や関連事業者が連携して開発し、価値に見合った合理的な価格で提供 出典:農林水産省「農業DX構想 ~『農業×デジタル』で食と農の未来を切り拓く~(要約版)」 |
つまり、単に農業の現場にIT技術を導入するだけでなく、それによって課題を解決し、新しい農産物の市場を切り拓いたり、これまでになかったビジネスモデルを構築したりして消費者ニーズに応えて行くことが「農業DX」だといっていいでしょう。
1-2.農業DXとスマート農業の違い
農業DXと似た言葉として、「スマート農業」というものがあります。両者の違いはなんでしょうか?
農林水産省では、「スマート農業」を「ロボット技術やICTを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業」(農林水産省ホームページ「スマート農業」より引用)としています。
つまり、スマート農業はデジタル技術を用いて効率化、高品質化を行う農業ということになります。
一方「農業DX」は、前述したように単にデジタル技術を農業に活用するだけでなく、農業の課題を解決することや、消費者ニーズに応えて新たな価値を提供することまでが含まれます。
ということは、スマート農業は農業DXの一部、手段であって、その先の成果まで求められるのが農業DXだと考えればいいでしょう。
2.農業DXの事例
農業DXとはどんなものか、大枠はつかめたかと思います。が、「もっと具体的に知りたい」という人も多いでしょう。
そこでこの章では、実際に農業においてDXに成功した事例を、国内・海外それぞれ紹介しておきましょう。
2-1.日本の農業DX事例
まず、日本での農業DXの事例です。農林水産省では、ホームページでいくつかの事例を紹介していますので、その中からピックアップして紹介します。
2-1-1.宮城県石巻市「たかはし農園」:AI病害虫雑草診断アプリ「レイミー」活用で生産性向上
宮城県石巻市の「たかはし農園」は、稲とネギの生産を行なっています。
会社員だったご主人が、父親の農地を引き継いで新規に就農したため、生産性の向上や作業の効率化を重視し、デジタルツールの導入にも積極的なようです。
その中で、2021年に導入したのがAI病害虫雑草診断アプリ「レイミー」でした。
これは、作物を撮影すると、瞬時に考えられる病害虫や生育障害の候補を表示することができるアプリです。
診断の確度や、その病害虫や生育障害に対してどのような農薬が登録されているかも表示されるため、対策まで立てることができます。
「たかはし農園」では、農作業の前にスマホで撮影しながら圃場を歩くことを日課にしていて、「レイミー」により生産性を向上させることができたそうです。
出典:農林水産省ホームページ
「農業DXの事例紹介(13)AI病害虫雑草診断アプリを活用して生産性を向上」
2-1-2.鹿児島県枕崎市「菊屋」:データ活用で適切な価格設定や設備投資が可能に
鹿児島県枕崎市の「菊屋」は、菊を生産している花き農家です。
2021年に県主催の研修に参加したところ、「スター農家クラウド」という農業向けの経営管理サービスを知って導入を決めたそうです。
このサービスでは、農業経営にデータを活用します。
「菊屋」では、毎日の菊の販売先と販売価格を入力、ひと目で確認できるようにしているそうです。
というのも、菊は種類や品質、需要などによって価格が変動しやすく、妥当な値段設定が難しいためとのこと。
それが、データを蓄積して確認しやすくすることで、適切な販売価格や販売先を判断できるようになったといいます。
また、売上が見える化されたことで、設備投資なども適切なタイミングでできるようになり、計画を立てやすくなったとのことです。
出典:農林水産省ホームページ「農業DXの事例紹介(8)データを活用した農業経営の改善」
2-1-3.栃木県塩谷郡「加藤いちご園」:圃場モニタリングシステムでいちごを安定した環境で栽培
栃木県塩谷郡の「加藤いちご園」は、人気の品種「とちおとめ」を栽培している農園です。
近隣ではIT技術を導入するのが早かったそうで、最初はいちごを作り始めて4作目の時に「温度記録センサー」を導入しましたが、データをうまく活用できなかったようです。
そこで、次に導入したのが「みどりクラウド」というモニタリングシステムでした。
これは、センサーによって圃場の環境や状況を記録、データ化するシステムです。
圃場が設定した温度の上限や下限に達すると、PCやスマートフォンにアラートが送られる機能もあり、予想外の温度変化にもすぐに対応できます。
これにより、いちごを安定した環境で育てることができるようになり、消費者が求めている「いつものいちご」を供給できるようになりました。
出典:農林水産省ホームページ
「農業DXの事例紹介(12)「いつものイチゴ」をつくるための温度管理、ITセンサー活用」
2-2.海外の農業DX事例
次に、海外の事例もいくつか紹介しておきましょう。
2-2-1.KaaIoT Technologies(アメリカ):農業DXで2050年までに農業生産性40%増、2030年までに食品ロス半減を目指す
アメリカでは、2020年にUSDA農業イノベーションアジェンダが公表されました。これは、
・2050年までに農業生産性を40%増加する
・2030年までに食品ロスを半減させる
などを目標として掲げるもので、この実現にはスマート農業の導入など農業DXが欠かせません。
民間企業も技術開発を進めています。たとえば、
・広大な農地での農作物の生育状況や環境のモニタリング、農薬散布などにドローンを活用
・衛星画像から農作物や土壌の状態をデータ化、各農家にアドバイスするサービスを提供
・GPSとAIを搭載したスマートトラクターを開発、圃場のどの部分をいつ収穫するかを計算して自動走行、自動収穫
といった例があり、ベンチャー企業などが新たな技術に挑戦している状況です。
2-2-2.オランダ:農家の8割が自動制御システムを導入、世界第2位の農業大国に
オランダは、国土面積は広くないながら、農産物・食料品の輸出額ではアメリカに次ぐ第2位を誇る農業大国です。農業や食品、ライフサイエンス等の研究に関わる大学・研究機関、企業を集約した「フードバレー」を形成して、先端技術の開発を進めています。
農業の現場にもDXが広がっていて、一般の農家の約8割が、自動制御システムを搭載したコンピューターを導入しているといいます。これにより、農作物に与える肥料や給水などを自動でコントロールできるのです。
また、巨大な農業用ハウスでは、内部の温度や湿度、CO2量などをセンサーで感知、コンピューターで管理しています。つねに作物にとってベストな環境を保つことができる仕組みです。
2-2-3.タイ:スマート技術の導入で生産性が30〜40%アップ
タイでは、2015年に政府が「デジタル化を加速させた付加価値創造社会を目指す長期的なビジョン」として「Thailand 4.0」を策定しました。
それを踏まえて農業分野では「Agriculture 4.0」を展開、スマート技術の導入に向けた取り組みを進めています。
たとえば以下のような取り組みがあります。
・デジタル経済振興庁(DEPA)が、74,000村にFreeWi-Fi Hotspotを設置
・スタートアップ企業「Smartfarm」が気象、土壌、水、作物のモニタリングシステムを開発。タイ全土からの情報収集・分析を支援
・農業・協同組合省(MOAC)と「Smartfarm」が提携している圃場で、計測センサーの導入やロボットトラクターの試験を実施
このようにスマート技術を導入することで、適切な播種ができ、収穫時期が確認できます。
それにより、生産性も30%~40%向上したそうです。
出典:JICA「農業・農村DX スマートフードチェーン ~JICAの取り組み~」
3.農林水産省が掲げる「農業DX構想」とは
農業DXは、国もその実現に向けて主導的役割をになっています。
その大きな取り組みのひとつが、農林水産省が掲げる「農業DX構想」です。
「農業DX構想」とは、農林水産省が「データ駆動型の農業経営により消費者ニーズに的確に対応した価値を創造・提供する農業(FaaS(Farming as a Service))への変革を進めるため、農業DXの意義・目的や基本的考え方、デジタル技術を活用した様々なプロジェクトを取りまとめた」(農林水産省ホームページ「農林水産業・食関連産業のデジタルトランスフォーメーション」ページより引用)もので、2021年3月に公表されました。
簡単に言い換えれば、「データを活用して消費者ニーズに応える農業=FaaSを実現するための構想」です。
たとえば、「農業 DX 構想 ~『農業×デジタル』で食と農の未来を切り拓く~」では、目指すFaaSの例として以下のようなものを挙げています。
| ・ 複数の自動走行トラクタの導入等により、少人数でも実行可能な超効率的な大規模生産を実現 ・ 土壌の生物性の状態の測定を効率的かつ的確に行うことにより、投入される化学肥料・化学農薬が必要最小限又はゼロとなり、コストの低減が実現されるとともに、生物叢の働きの活性化により化学肥料・化学農薬使用時とそん色のない収量を実現 ・ 消費者の購買データを元に需要の変化をつかみ、国内外の多様なニーズに機動的に対応した食料の生産を行い、供給することで、消費者の支持を獲得 ・ 作業の省力化や自動化に加え、AI の活用により予測の精度が上がることで、やる気のある農業者であれば、体力的にきつくなってきた高齢者であっても、就農してからの期間が短い若手であっても、品質の高い農産物を安定的に生産できる経営を実現 ・ 地理的条件の不利な地域であっても、新技術の活用や土壌の特質に応じた適地適作を効率的に実行し、他の土地では生産することができない高い価値を持つ農産物として、適切な価格で販売 ・ 好天候による豊作や需要の変化により余剰が発生しそうになっても、新たな需要先(取引先)とのスムーズなマッチングや消費者のし好に応じた調製・加工を行うことにより、大きな値崩れを起こすことなく出荷 ・ 消費者のし好(「味」や「栄養」はもとより、食を通じて感じられる価値(安全・安心、健康・体質改善、一家団欒、倫理的消費など))にあった食品を、農業者や関連事業者が連携して開発し、価値に見合った合理的な価格で提供 ・ 人の胃腸の検査データを基に、個人の腸内フローラの特性を割り出し、その働きを活性化する食べ物や食生活を提案するとともに、それに応じた農産物・食品を生産・製造し、販売 ・ 緊急時に、消費者のし好を中心とした供給から、人間の生存に必要な量・栄養価を公正に提供できる体制に大きな支障なく切り替え 出典:農林水産省「農業 DX 構想 ~『農業×デジタル』で食と農の未来を切り拓く~」 |
前掲した要約版の例と一部重複しますが、農業DXやFaaSが単なるデジタル技術の導入にとどまらないことがわかるでしょう。
農林水産省では、農業DXを2030年に実現することを目指しています。
4.農業DXでできることとメリット
ここまで読んで、「自分のところでも農業DXに取り組みたいが、どんな技術を取り入れればいいのだろうか?」「どんな成果が得られるのだろう?」と疑問や不安を抱く人も多いでしょう。
そこでこの章では、農業DXに関してどんなデジタル技術を導入すれば何ができるのか、その結果どんなメリットが得られるのか、主なものをいくつかまとめてみました。
・AIによる収穫予測→需要に則した供給
・農業機械の自動運転→人手不足の解消
・センシングによる適地適作→生産性向上
・ドローンによる薬剤散布や播種→作業の効率化
それぞれ説明します。
4-1.AIによる収穫予測→需要に則した供給
農業DXにおいてAI(=人工知能)が活用できることのひとつに、「収穫予測」が挙げられます。
気象情報、土壌に関するデータ、過去の収穫データなどさまざまなデータをもとに、AIが「どの作物が、いつ、どれくらい収穫できるか」を予測します。
これにより、消費者の需要に合わせた生産計画を立てることができるようになります。
収穫量が足りずに価格が高騰したり、逆に獲れすぎて廃棄しなければならなくなったりということが減り、安定した出荷が可能になるでしょう。
【AIによる収穫予測を行うソリューションの例】
導入効果が期待できる農家は… |
・安定した出荷をしたい農家 など |
4-2.農業機械の自動運転→人手不足の解消
車の自動運転技術は、農業機械にも取り入れられています。
トラクターや田植え機、コンバインなどがGPSの位置情報をもとに自動走行するのを、離れた場所からタブレットなどでコントロールすることが可能です。
これを導入すれば、トラクターが自走して畝を作る後ろから人が運転する農機具で作物の苗を植える、といった同時作業も実現します。
人力で行う作業を減らせることで、人手不足の解消につながるでしょう。
【自動運転する農業機械の例】
導入効果が期待できる農家は… |
・人手不足で悩んでいる農家 ・作業を効率化したい農家 など |
4-3.センシングによる適地適作→生産性向上
農業では、その土地や環境に合った作物を育てる「適地適作」が重要です。
これができていれば、品質のいい農作物が豊富に生産できるためです。
そのために、「センシング」が活用されています。
圃場にセンサーを設置し、温度、湿度、照度、水分、CO2、pH、土壌、NDVI(育成度)などを感知、その情報を分析する技術です。
離れた場所にいても、圃場の状態が数値で把握できるので、「温度が高め」「水分が足りない」など問題があればすぐに適切な対策をとることができます。
これにより、つねに最適な状態で農作物を育てることができ、品質も生産性も向上するでしょう。
【センシング技術の例】
導入効果が期待できる農家は… |
・農地が複数箇所あって、それぞれをまわる手間が負担になっている農家 ・就農経験が長くはなく、知識や経験に不安がある農家 など |
4-4.ドローンによる薬剤散布や播種→作業の効率化
農業向けのデジタル技術として近年導入が進んでいるのがドローンです。
農業用ドローンで空から農薬を散布したり、種を蒔いたりするのです。
離れた場所に畑が点在している場合などは、これまで人がそれぞれの畑をまわって作業をしなければなりませんでした。
それがドローンなら、人は1か所にとどまってドローンを操縦するだけで、あちこちの畑に農薬や種を蒔くことができるようになります。
そのため、作業が大幅に効率化されるでしょう。
体力が衰えてきた高齢者でも、ドローンを用いれば負担なく作業することができるはずです。
【農業用ドローンの例】
・DJI JAPAN「AGRAS T20 日本版」
・マゼックス 農業用ドローン「飛助ーtobisukeー」
導入効果が期待できる農家は… |
・農地が複数箇所あって、それぞれをまわって作業する手間がかかる農家 ・高齢化して農薬散布や播種の作業が負担になっている農家 など |
これ以外にも、さまざまな技術が農業分野に導入されつつあります。
農林水産省では、「デジタルトランスフォーメーションにより実現する農業の未来」として以下のような仕組みを描いています。
出典:厚生労働省「農業のデジタルトランスフォーメーション(DX)について」
5.農業DX実現への課題
このように、官民力を合わせて推進している農業DXですが、実際に農業従事者が導入する際にはいくつか課題もあります。たとえば以下のような点です。
・デジタル技術に対応できない
・導入コストが必要
・法整備が不十分
5-1.デジタル技術に対応できない
まず、農業従事者の中にはデジタル技術に対応できない人もいます。どんな技術を導入すればいいのか、どう活用するのかわからない、となるとDXは進められません。中には「農業にはデジタル技術は必要ない」と考える人もあるでしょう。
これには人によってさまざまな原因があるはずです。
「そもそもデジタルが苦手」「数値化されたデータよりも、長年の経験やカンに従いたい」「これまでのやり方を大幅に変えるのは面倒」など、いろいろな声が上がるでしょうが、それらを払拭してDXに取り組んでもらうには、まずDXの必要性を理解させる必要がありそうです。
人手不足が解消されること、生産性が上がること、年配者でも作業が楽になることなどメリットを説明して理解を得ましょう。
また、最初から大々的に導入するのではなく、受け入れやすい簡単なものから取り入れる工夫も必要です。
必要なデジタル技術やソリューションをリストアップして、デジタルが苦手な人でも対応できそうなものから段階的に導入するといいでしょう。
5-2.導入コストが必要
もうひとつ、大きな問題になるのが導入コストです。農業に関するデジタル技術は数十万〜数百万円するものも多く、DX化を始めるためには最初にある程度の予算を確保しておかなければなりません。
ただ、小規模な農家ではそれだけの費用を用意できないところもあるでしょう。
そんなときは、補助金などを利用することを検討してみてください。
たとえば国の補助金には以下のようなものがあります。
助成金・補助金 | 概要 | 受給の条件と金額 |
経済産業省・中小企業庁による補助金。 IT導入やDXによる生産性向上をはかる企業に支給される。 | 生産性を向上させる目的でのITツールの導入費用 補助金額:最大450万円 | |
経済産業省・中小企業庁による補助金。 中小企業・小規模事業者が革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うために設備投資する場合に支給される。 DXの場合は「デジタル枠」で申請する。 | DXに資する革新的な製品・サービス開発又は⽣産プロセス・サービス提供方法の改善による⽣産性向上に必要な設備・システム投資など 補助金額:750万〜1,250万円 | |
経済産業省・中小企業庁による補助金。 小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓のために支給される。 | 販路開拓のための設備導入、チラシ・パンフレット、ホームページやウェブ広告、店舗の改装、展示会の出展、新商品の開発費用など 補助金額:50~200万円 |
これ以外にも、期間限定で募集する補助金もありますし、各自治体でも補助金制度を設けているところがあるはずです。
自分の住んでいる自治体に利用できる補助金がないか、役所などで確認してみましょう。
5-3.法整備が不十分
ITやデジタル技術に関しては、まだ法整備が十分ではない部分もあります。
たとえばドローンに関しては、飛ばすことができる場所や方法に法律で制限が設けられています。人口集中地区や空港周辺などを飛ばすには、事前に国土交通省に許可申請をしなければなりません。夜間に飛ばす場合や、操縦者が目視できない範囲で飛ばす場合にも許可が必要です。危険物を運ぶ場合やドローンからものを落とす場合も同様ですので、農業用ドローンで農薬を散布する際には許可申請をします。
しかし、ドローンに関する法律はしばしば改正されたり新たに作られたりしています。
実際に、これまでは「第三者上空の目視外飛行」は法律で認められていませんでしたが、2022年12月に、国家資格などの条件を満たした人が事前に申請すれば、許可されるようになりました。
というのも、ドローンを各産業で活用するには「第三者上空の目視外飛行」をする必要があるからです。
このように、デジタル技術に関する法律は、技術の進歩や社会の要請などに合わせて今後整備が進んでいくはずです。
農業DXを推進するには、関係する法律についても随時確認していく必要があるでしょう。
6.農業DXが向いている農家とは

さて、ここまで農業DXについて説明してきましたが、すべての農家がDXをすべきなのでしょうか?もちろん、可能であればどんな農家でもDXに取り組んで生産性を上げるのが望ましいでしょう。ただ、規模や費用を考えて、導入をためらってしまう農家も多いはずです。
そこで、「農業DXが向いているのでぜひ取り組んでほしい農家」の特徴を以下にまとめました。
DXが向いている農家とは |
・人手が不足している ・作業を効率化して生産性を高めたい ・新たな事業を生み出したい |
これに該当するのであれば、ぜひDXを検討しましょう。
\農業のDXは『デザインワン・ジャパン』にご相談ください/
DXを推進しようと思っても、「何から始めればいいかわからない」「どんなシステムやツールが適しているか選べない」などと悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
デザインワン・ジャパンでは、アイディアの創出やビジネス設計から、開発・保守運用までDX推進に必要な全工程を一貫して支援する「DXソリューション」を提供しています。
事業開発ディレクター・コンサルタント・デザイナー・開発エンジニアなど各分野のスペシャリストがビジネスパートナーとしてDXを支援します。
ご相談・お見積りは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
7.まとめ
いかがでしたか?
農業DXについて知りたいことの答えが得られたかと思います。ではあらためて、記事の内容を振り返ってみましょう。
◎農業におけるDXとは、単に農業の現場にIT技術を導入するだけではなく、それによって課題を解決し、新しい農産物の市場を切り拓いたり、これまでになかったビジネスモデルを構築したりして消費者ニーズに応えて行くこと
◎農業DXでできることとメリットは、
・AIによる収穫予測→需要に則した供給
・農業機械の自動運転→人手不足の解消
・センシングによる適地適作→生産性向上
・ドローンによる薬剤散布や播種→作業の効率化
◎農業DX実現への課題は、
・デジタル技術に対応できない
・導入コストが必要
・法整備が不十分
これを踏まえて、あなたが農業DXに取り組めるよう願っています。

 dx
dx