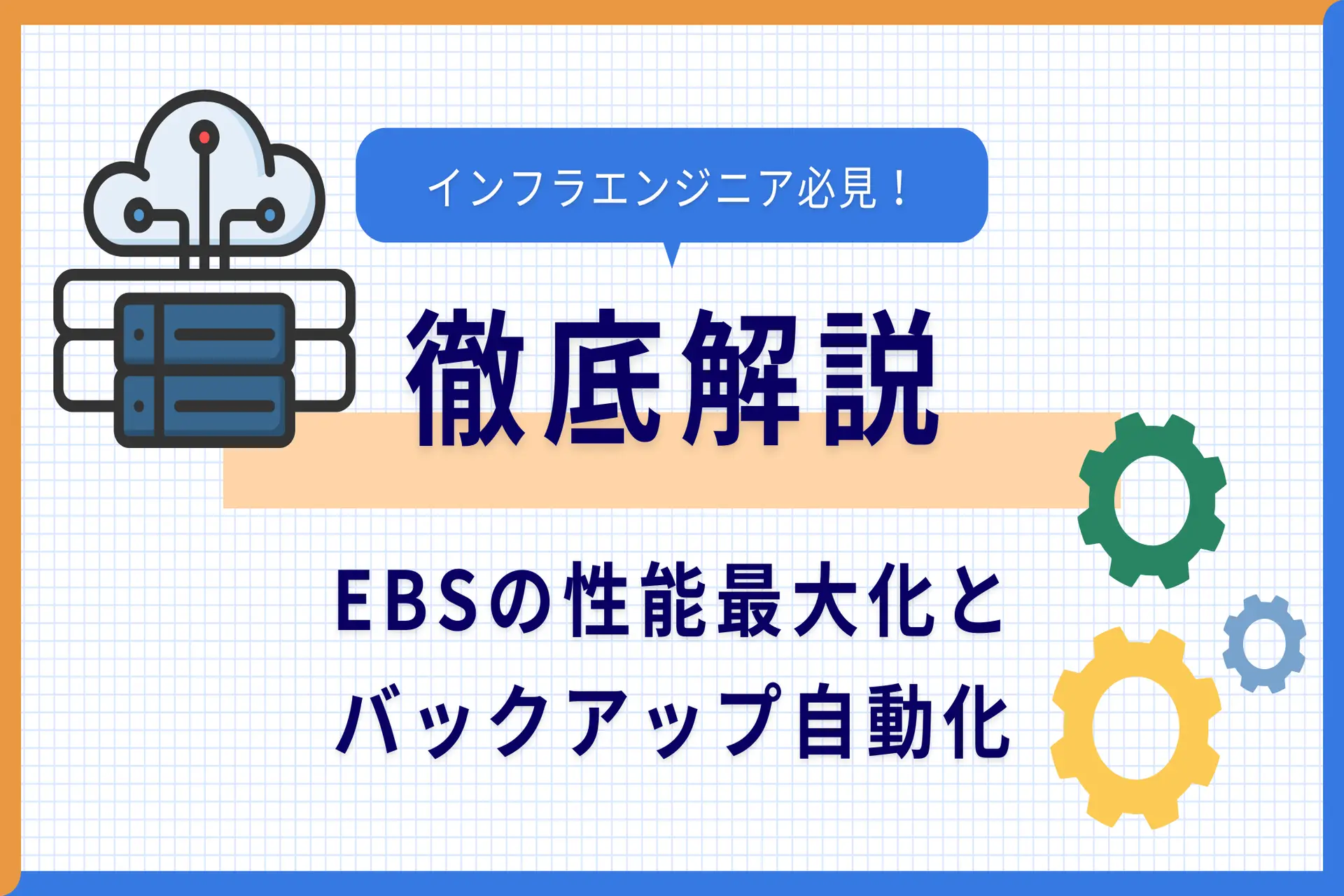DX推進の弊害と成功の鍵とは?中堅・中小企業が直面する課題とその打開策
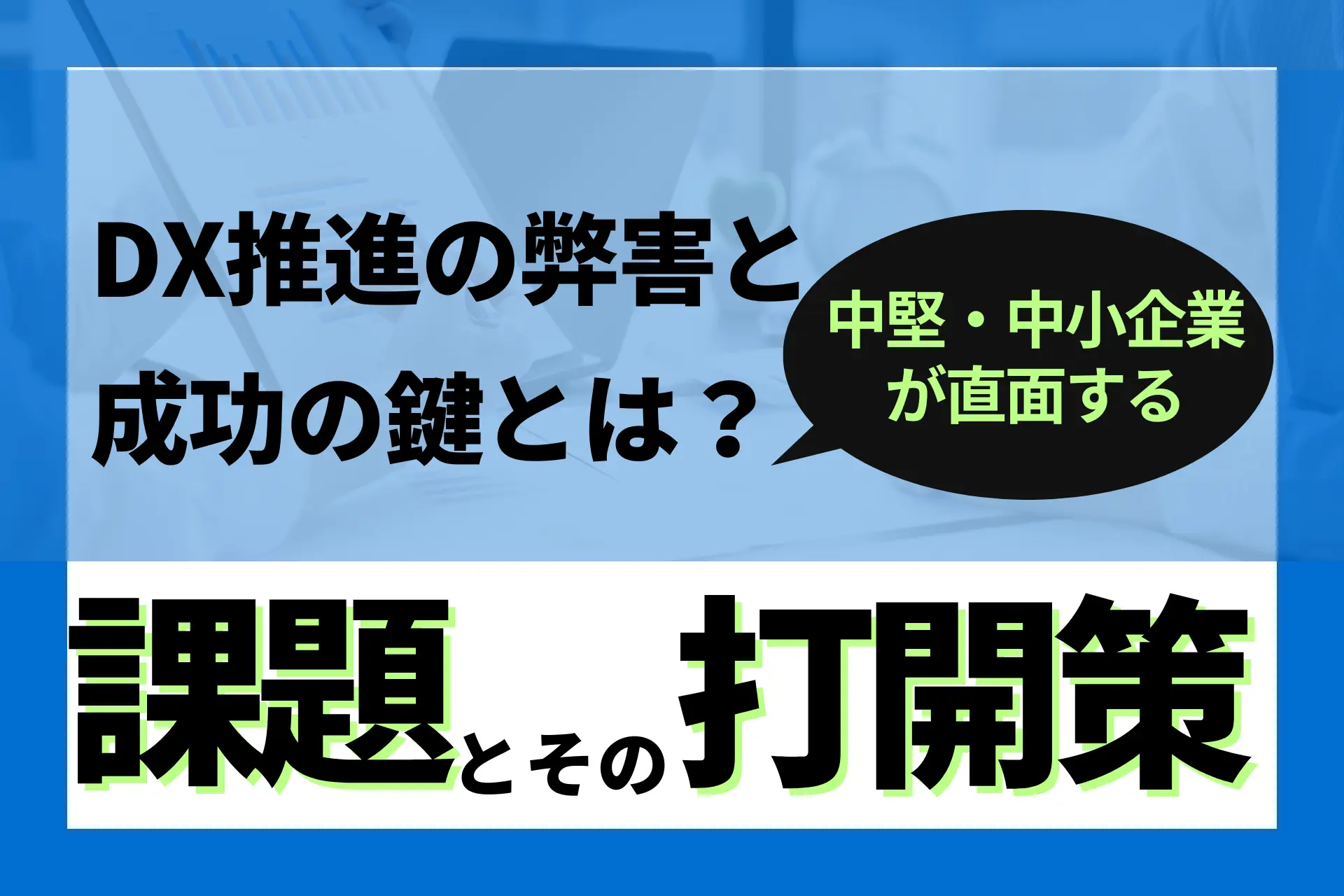
目次
1. DXの弊害とは何か?
そもそも、DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して、企業のプロセスやビジネスのあり方、さらには社内文化までも変化させる試みです。
単なる業務効率化だけではなく、「企業が変化する市場環境に柔軟に対応し続ける力」を得ることを目的としています。
したがって、システムを導入するだけで終わらせず、「それをどう活かすか」が鍵となるため、DXの本質的な理解ができていないと効率化とは程遠い結果におちいってしまう可能性があります。
DXの弊害として上げられることの一つが、DXの本質的な目的をどこまで理解できているか。ということになります。
2. 「2025年の崖」とは何か
DXが必要とされる背景のひとつに、経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」問題があります。
これは、現在企業が使い続けている古い情報システム(レガシーシステム)が限界を迎え、業務効率を妨げ、競争力の低下をもたらす危険があるという指摘です。
実際、多くの企業でERPなどの基幹システムが複雑化し、誰がどう設計したかすら分からないブラックボックスになっています。
ここでは、2025年に向けて何が課題なのか、そしてその弊害が企業にもたらす具体的なリスクについて解説します。
2-1 経済産業省が警鐘を鳴らす背景
経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」では、日本企業の多くが古くて複雑なITシステムを抱え続けている事実が浮き彫りになりました。
これらのレガシーシステムがあるために、新しいサービスの展開や市場の変化への対応が遅れがちで、今後その差がますます広がると予測されています。
このままでは2025年以降、年間で最大12兆円もの経済損失が生じる可能性があるとされ、まさに企業にとって"崖"のようなリスクとなっていくのです。
DXを避け続けることは、経営判断の遅れや国際競争力の低下に直結します。
2-2 想定される経済的損失とその要因
2025年の崖で予測されている経済損失の要因は、大きく3つに分けられます。
第一に、老朽化したシステムの維持管理に費用がかかり、IT予算が新しい挑戦に使えないこと。
第二に、業務やデータが属人化し、異動や退職によりノウハウが失われるリスク。
第三に、すでに導入済みのシステムが他社製品と連携しづらく、柔軟な業務変化に対応できない点です。
これらが足かせとなり、企業の持続的成長を妨げるのです。
2025年の崖は単なる予測ではなく、多くの企業が今すでに直面している現実の問題なのです。
2-3 古いシステム(レガシーシステム)のリスク
レガシーシステムとは、長年使い続けられ更新が難しくなった古い情報システムのことを指します。
一度この体制が固定されると、担当者以外には内容が理解できなかったり、「その人がいないと動かせない」という状態になりやすいです(属人化)。
また、セキュリティ上の脆弱性が放置される危険性も高く、ひとたび障害が発生すると事業への影響は甚大になります。
さらに現代的なクラウドサービスやAI技術との連携も困難になるため、本来なら獲得できた競争優位性を逃す要因にもなります。
DXを進めるにはまずこのリスクを直視し、確実な移行計画を立てる必要があります。
3. DX推進を阻む3つの主要課題
DXの必要性が明確になっても、それを実行に移す過程では大きな障壁に直面します。
特に地方に本社を置く中堅・中小企業の現場では、「どうやって進めればよいのか分からない」という声が多く聞かれます。
主な課題は3つ、「技術的な問題」「組織的な構造の問題」「人材の不足」です。
これらの課題が絡み合っているため、解決には経営層の理解と全社的な連携が欠かせません。
ここでは、DX責任者が直面しがちな課題について、詳しく分かりやすく解説します。
3-1 技術的課題:老朽化システムと複雑なIT環境
技術的な課題の多くは、先ほど紹介したレガシーシステムに起因しています。
古いシステムが複数混在し、連携が複雑になっていることで、新しいクラウドサービスやAI技術の導入が困難になるケースが非常に多く見られます。
そもそもシステムの設計情報が散逸しており、誰もその全体像を把握していない「ブラックボックス化」が起きています。
さらに、IT予算の多くが既存システムの保守運用に使われてしまい、新たな取り組みに投資する余裕が生まれないという悪循環も問題です。
これは、現場担当者だけでは解決できない根深い課題であり、全社的なIT戦略の見直しが求められます。
3-2 組織的課題:縦割り構造と意思決定の遅さ
組織内部の構造もDXを阻む大きな要因です。
部門ごとの「縦割り構造」が根強く残っている組織では、全体最適よりも部門最適を優先する傾向があり、DXのように全社的な変革には反発が起きやすくなります。
また、稟議(りんぎ)など複雑な承認プロセスにより、意思決定のスピードが遅れがちというのも深刻な問題です。
経営層から「進めろ」と言われても、途中で止まってしまうプロジェクトが多いのはこのためです。
DXはスピードと柔軟性が大切ですが、それに対応するための組織体制が整っていないまま進めようとすれば、苦戦は避けられません。
3-3 人材的課題:IT人材の不足とスキルギャップ
DXを成功させるには、技術に明るく、かつ業務理解も深い人材が必要です。
しかし多くの中堅・中小企業では、IT人材が不足しているうえ、既存社員が新しいツールや考え方に馴染めていないという「スキルギャップ(能力の差)」が問題になります。
IT技術の進化は非常に早く、特にデジタルネイティブ世代ではないベテラン社員にとって、新しいシステムや用語は馴染みにくいものです。
また、社外に頼り切ることでますます自社にIT知見が蓄積されず、ベンダー依存が加速してしまうという悪循環にも注意が必要であり、人材育成の重要性は非常に高いテーマと言えるでしょう。
4. DXの弊害とは何か
DXは企業の持続的な成長に欠かせないキーワードとなっていますが、その推進が必ずしも成果に結びつくとは限りません。
むしろ、DXという言葉そのものが一人歩きし、本来の目的を見失ったままプロジェクトを進めた結果、多くの問題を引き起こしてしまうケースもあります。
この章では、DX推進中もしくは導入を検討中の企業が注意すべき「DXの弊害」について解説します。
「何から手をつければ良いか分からない」と感じている担当者にとって、ここでの内容は特に重要です。
4-1 DXの誤解と概念の混乱
「DX=システム導入」「新しいツールを使えばDXになる」といった誤解は非常に多く見られます。
本来、DXとは単なる技術導入ではなく、業務プロセスやビジネスモデルを見直し、組織の文化そのものを変えるような根本的な取り組みです。
「とりあえず流行りだから導入する」といった表面的な動機では、従業員の理解も得られず、現場の混乱を引き起こす可能性があります。
また、部門ごとに異なる解釈で進めてしまうと、システムがバラバラに導入され、結果的に全体最適がなされなくなります。
DXの本質を共有し、組織全体で共通認識を持つことが最初のステップとなるのです。
4-2 性急な投資による失敗リスク
経営判断のスピードが求められる中、業界や競合に遅れを取るまいと、十分な準備をせずに高額なシステムを性急に導入してしまうケースも珍しくありません。
その結果、期待した効果が出ず「無駄遣いだった」と評価され、次の投資が社内的にしにくくなるという悪循環が起こりがちです。
DXには明確なゴール設定と費用対効果(ROI=Return on Investment:投資収益率)の評価が欠かせません。
導入前に「なぜDXが必要なのか」「どの業務をどう変えたいのか」を見極め、段階的な投資スケジュールを組むことが成功の鍵です。
4-3 システムブラックボックス化
ITベンダーに丸投げし続けた結果、システムの仕様書やソースコードが社内に残っておらず、「中身が分からない」システムになってしまうことがあります。
この状態では、不具合が起きても自社では何も対処できず、修正や改修に時間とコストがかかるばかりか、外部依存が強化されることになります。
さらに、異なるベンダー間の引き継ぎが困難になり、将来的な更新や変更の自由度も大きく損なわれてしまいます。
DXを進める際は「自分たちの業務に必要なシステムをどう設計し、どこまで自社で把握するか」という姿勢が非常に重要です。
5. DXの成功に必要な視点
DXの推進において重要なのは、闇雲にツールやシステムを導入するのではなく、「なぜ取り組むのか」「どこに価値を置くのか」という視点を持つことです。
つまり戦略的なアプローチがなければ、かえって無駄な投資や組織の混乱を引き起こすリスクが高まります。
この章では、DXを本質的に成功させるために必要な視点や考え方について、具体的に見ていきましょう。
5-1 戦略的IT投資とROIの明確化
「とにかく導入する」ではなく、「何にいくら投資し、どれだけの見返りがあるか」を明確にすることがDX成功の基本です。
ROI(投資収益率)を意識し、システム導入がどれだけ業務効率や売上向上に寄与するかを数値で示せるようにしましょう。
例えば、生産ラインの監視をIoT化する場合、それによってどれほどリードタイム(納品までの時間)が短縮されるのか、メンテナンスコストがどれくらい削減されるのかを事前に可視化し試算することが求められます。
経営層や現場への説得材料としても、投資に対する成果を明確に示すことが欠かせません。
5-2 経営層のリーダーシップとビジョン共有
DXは、単なるシステム導入のプロジェクトではなく「経営の改革」といえる取り組みです。
そのため、経営層自らが主導的に関わらなければ、現場に浸透することはありません。
「なぜDXを進めるのか」「会社としてどんな未来を目指すのか」といったビジョンを明確に打ち出し、それを全社員と共有することが必要です。
ただ現場からの要望を受けるだけでなく、経営層との橋渡しとなり、企業全体でDXに向かう統一的な方向性を作ることが極めて重要です。
ビジョンの共有がなければ、DXは単なる部門ごとの一過性の取り組みで終わってしまいます。
5-3 アジャイル導入と継続的改善文化の醸成
アジャイルとは、小さな単位でシステムや機能を開発し、短いサイクルで改善や修正を繰り返す方法論です。
DXは一度に大きく変えるのではなく、段階的な改善の重ね合わせで成長させていくものです。
そのため、アジャイル的な考え方を導入することで、現場の声を反映させながら柔軟な開発や運用が実現できます。
こうした柔軟な体制とともに、「失敗を恐れずに試す文化」「改善を続ける風土」を社内に根付かせることが、DXを持続可能なものにする核心です。
6. IT予算の最適配分方法
限られたIT予算の中で効果的にDXに取り組むには、予算の使い方自体を見直す必要があります。
多くの中堅・中小企業では、現行システムの維持管理に費用の大半が充てられ、革新的な取り組みに回る余地が少ないのが現状です。
この章では、今あるリソースをどう使い、将来の企業力につながる予算配分をどう実現するかについて考えていきます。
6-1 維持管理費のスリム化戦略
年間IT予算のうち、7割以上が「システムを壊さず維持するコスト」に消えている企業も少なくありません。
この維持管理費を削減することが、DX予算の捻出につながります。
具体的には、外注作業の内製化、重複機能を持つシステムの統廃合、不必要な保守契約の見直しなどが有効です。
例えば、社内でよく使われるExcel帳票を簡易なクラウドシステムに統一するだけでも、管理の手間とトラブルが激減し、保守コストも低下することがあります。
こうした取り組みは短期的な投資で中長期的に大きな節約効果をもたらします。
6-2 DXへの投資比率を高める方法
維持費を削減できた分、次に重要なのは「投資対効果が高い部分に集中投資する」ことです。
例えば、日報や勤怠管理など、社員の日常業務に関係する部分を自動化することで、全社的な生産性を底上げできます。
また、営業やマーケティング部門といった収益に直結する部門へのIT支援も、早期に成果を可視化しやすくおすすめです。
「全てをDX化する」のではなく、「費用対効果が分かりやすく、社内の成功体験を生みやすい箇所」から着手することが、社内に理解と支持を得る近道です。
6-3 クラウド移行によるコスト効率の向上
オンプレミス(自社でサーバーを保有管理する形態)からクラウドへとシステムを移行する企業が増えています。
クラウドサービスの導入により、初期投資を抑えつつ維持費を定額化できるうえ、必要な時に必要なだけ使える柔軟性も得られます。
また、自動バックアップやセキュリティ対策もセットで提供されることが多く、自社での管理負担も軽減可能です。
クラウド化は単なるコスト削減策にとどまらず、スピード感のある業務改善の土台としても非常に有効です。
7. DXの成功事例と学ぶべき教訓
DXの取り組みは理論だけでなく、現実の現場でどう実行され、どんな成果や失敗につながったのかを知ることで、非常に多くの学びがあります。
ここでは、国内外の企業の成功・失敗事例を分析し、それぞれのケースから何を学び、自社のDX推進にどう活かせるかを整理して紹介します。
DXの方向性を検討している立場では、こうした事例を参照することで、説得力ある社内提案がしやすくなるでしょう。
7-1 国内企業の成功事例分析
例えば、ある地方の食品メーカーでは、製造から出荷、販売までを一体で管理するクラウド型生産管理システムを導入しました。
その結果、従来は紙で行われていた在庫管理がリアルタイム化され、欠品や過剰在庫が大幅に削減されました。
また、営業・製造部門の情報共有が進み、顧客対応のスピードも向上。
「まずは社内理解を得るため、現場に近い課題からITによる改善をスタートしたこと」が、プロジェクト成功の要因になったと振り返られています。
このように着実な成功体験の積み重ねが、社内にDX推進の土壌を築いていくのです。
7-2 失敗例からの反省点と改善策
一方で、ある製造業では社内の合意形成が不十分なままERP(基幹業務システム)の全面刷新を進めた結果、現場の反発を受け、稼働後すぐにトラブルが発生。
導入したシステムが現場の実態とかみ合っておらず、情報の入力ミスや操作方法の混乱が続出しました。
この事例は、「ユーザー視点の欠如」や「変化を受け入れる体制づくりの不足」が、DXを遠ざけてしまうことを示しています。
事前に現場のニーズを丁寧にヒアリングし、段階的に進めながら社内の合意形成を取ることの重要性が改めて浮き彫りとなるケースです。
7-3 グローバル企業との比較による示唆
海外の先進企業では、DXにおいて「失敗しても学ぶ」という文化が根付いています。
北欧のある企業では、AIを使った製造ラインの品質管理を試験的に導入したものの、初期は思ったように精度が出なかったそうです。
しかし、問題点を早期に抽出・修正し、6ヶ月間で精度は95%以上に向上。成功体験を社内で共有し次の導入部門へ展開する仕組みが整っていました。
グローバル企業のDX推進には、柔軟性のある開発手法と、組織全体でのスピーディな試行錯誤がセットであることが特徴です。
この姿勢から学べることは非常に多いでしょう。
8. DXを支援するインテックのアプローチ
DXを社内だけで進めるには、多くの知識・経験・技術が求められます。
実際、DXにおいては専門知識を持った外部パートナーの支援が成果に直結する重要な要素にもなっています。
ここでは、インテックがどのような支援を通じて企業のDX実現をサポートしているのかご紹介します。
8-1 ソリューションとサービス紹介
インテックでは、業種や企業規模を問わずDX支援を行う各種サービスを展開しています。
例えば、現行システムの分析支援から始まり、無理なく改善・更新できるロードマップの策定、中長期的なIT戦略の立案までをトータルで支援。
さらに、IoT・AI・クラウドなどの最新技術の導入にあたっても、業務に即したソリューションを提案します。
技術力だけでなく、業務理解に基づいたコンサルティングを強みとしています。
8-2 課題ごとの支援体制と導入プロセス
企業によって課題や目的はさまざまです。
そのため、インテックでは「現場ヒアリング→業務分析→課題整理→段階別実行案の策定」というステップで個別対応するアプローチを採用。
現場の視点を重視し、無理な全面刷新ではなくスモールスタートで改善を始めることで、社内の理解と合意形成を丁寧に育てる方針です。
また、プロジェクト終了後もフォローアップ体制を継続し、長期にわたる伴走支援を行っています。
8-3 顧客事例に学ぶDX実現ステップ
ある中堅・中小流通企業では、インテックの支援により紙で行っていた受発注業務をクラウドシステムに置き換えたところ、受注対応時間が約40%短縮し、在庫管理ミスも大幅に減少しました。
この企業は段階的な導入によって現場の納得感を高め、結果的に社内全体の業務見直しにもつなげることができました。
「現場を巻き込むこと」と「わかりやすい成果をつくること」の両輪が、DXにおいて極めて重要であることを体現した成功事例です。
9. 今後のDX戦略に必要なマインドセット
最後に、DXを長期的に成功へ導くために必要な「考え方=マインドセット」について触れておきましょう。
「システム導入が終わればDX完了」という認識は誤りです。
むしろそこからが本当の業務改革、組織変革の始まりです。
企業が環境に適応し、新しい価値を生み出し続けられるようになるための思考と行動様式について考えていきます。
9-1 ビジネス変革への主体的思考
変化に対して受け身でいるのではなく、「自分たちの業務をどう変革すべきか」を主体的に捉える視点が重要です。
外部環境や市場の動きを敏感に捉え、今までの前提を疑い、柔軟かつ能動的に行動する文化を育てていく必要があります。
例えば、製造企業であれば、単にコスト削減ではなく「高付加価値の製品づくりに向けた工程の見直し」がDX推進の着眼点となることもあります。
9-2 デジタルを活用した付加価値創造
DXの本質はコスト削減以上に、「新しい価値をいかに創造するか」にあります。
例えば、顧客データを分析しニーズに合った製品を提案したり、IoTで収集した稼働データを元に保守サービスを提供するなど、デジタルを戦略的に活用することが差別化につながります。
「儲かる仕組みをソフトウェアで作る」ことが、これからの企業には求められています。
9-3 未来志向の組織づくりと人材育成
DXは一過性のブームではなく、今後も加速度的に進化し続ける企業経営の根幹となるテーマです。
そのためには、未来に適応できる柔軟性と学習力を持った人材を計画的に育成し、変化に強い組織構造を整えることが不可欠です。
「教育」「風土づくり」「継続的な改善」という3つの柱を中心に、全社的な構造改革を進めていく必要があります。

 dx
dx