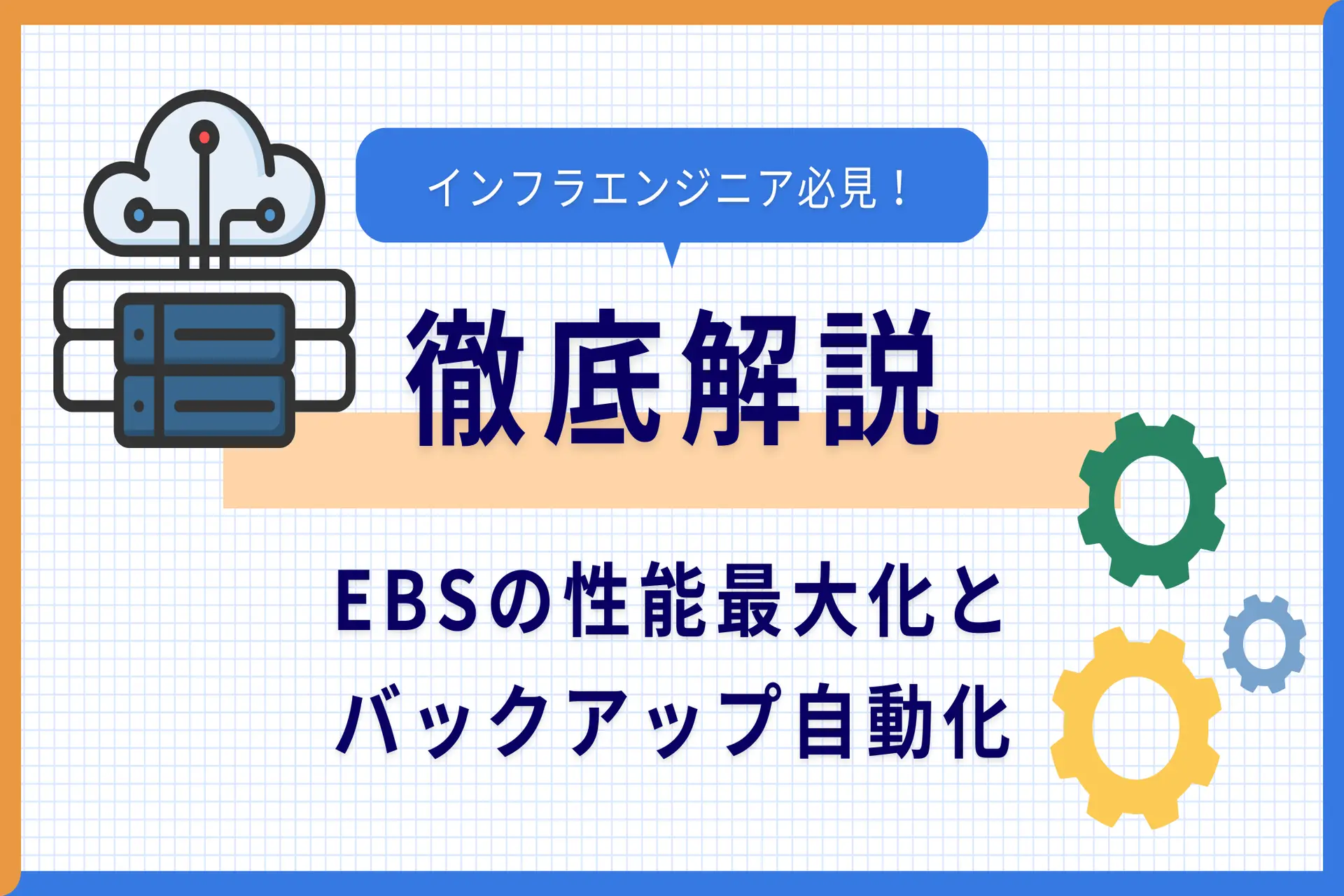自治体職員のためのDX推進入門:住民視点とリスク対策から導く持続的改革
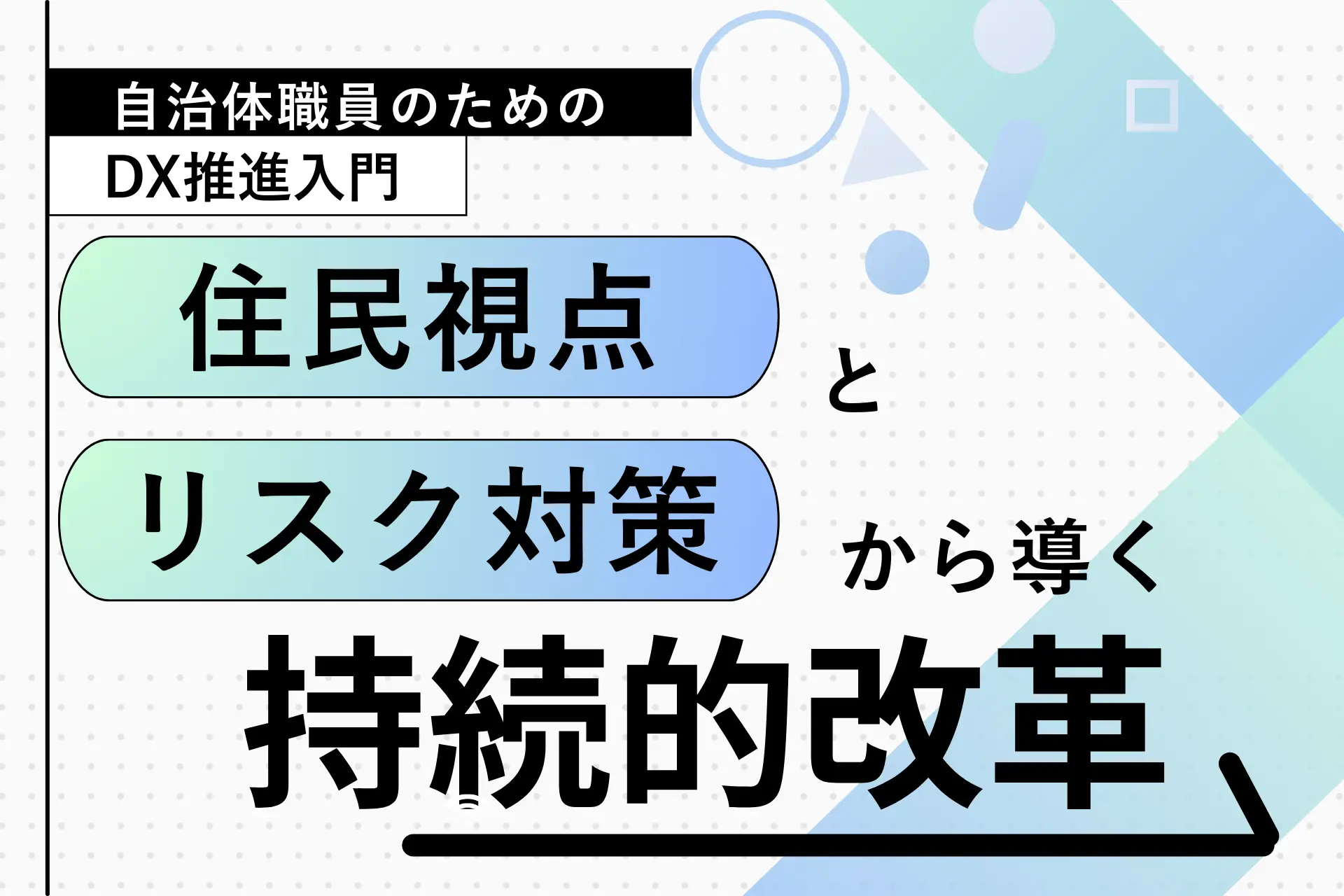
目次
1. 自治体DXとは何か
デジタル技術の進展により、私たちの暮らし方や働き方が大きく変わりつつあります。行政機関も例外ではなく、自治体が直面する人口減少・高齢化・労働力不足といった課題に対応するためには、デジタル変革(Digital Transformation/DX)の推進が不可欠です。ここでは、自治体DXの基本を押さえつつ、実務担当者が実際に現場で活用できる視点から解説していきます。
1-1 DXの定義と地方自治体における重要性
DXは「Digital Transformation(デジタル・トランスフォーメーション)」の略で、単なるシステム導入ではなく、デジタル技術を活用して業務プロセスや組織のあり方を根本から見直し、住民サービスをより良くしていく取り組み全体を意味します。民間企業では利益追求のために進められるDXですが、地方自治体の場合は「住民サービスの向上」「業務効率化」「地域の持続可能性の確保」という目的があります。とりわけ中規模の自治体では、限られた職員数や財源で多くの行政需要に応える必要があり、DXの推進が喫緊の課題となっています。
1-2 日本政府・総務省の方針と背景
日本政府は「自治体DX推進計画」を打ち出し、地方自治体におけるDXを国全体で後押ししています。総務省も中心的な役割を担っており、全国統一の「自治体システム標準化」や「自治体クラウド」などを推進しています。その背景には、国全体として行政のデジタル化を進めることで、住民の利便性を高めたり、自治体間の業務のばらつきを解消する狙いがあります。この流れに沿って、各自治体はいま、自主的にDX推進体制を整える必要に迫られています。
2. 最新の制度・ガイドライン
「何から手を付けてよいかわからない」という声が多く挙がる自治体DXの現場において、制度やガイドラインの把握は第一歩です。国から発信されている最新の制度を正しく読み解き、各自治体の状況に応じて活用していく必要があります。
2-1 「自治体DX推進計画」の概要
2024年4月に最新版が公開された「自治体DX推進計画」では、自治体のDXを進める上での主要な方向性を全国統一の指針として示しています。内容は標準化・共通化、市民サービスの多様化対応、職員の学び直し(リスキリング)支援などが主軸です。中規模自治体にとっては、既存システムや予算との兼ね合いを見ながら、段階的な導入が求められます。
2-2 「自治体DX・情報化推進概要」の活用方法
「自治体DX・情報化推進概要」は、年度ごとの情報化施策の進捗や今後の展開がまとめられた資料です。特に自治体の情報政策担当者にとっては、他自治体の取り組みやその進行度をベンチマーク(比較基準)として活用できる点が非常に有効です。実際の計画立案やベンダー選定時に参照すると、自団体の立ち位置が明確になります。
2-3 「自治体DX全体手順書」の読み解き方
全国の自治体向けに総務省が公開している「自治体DX全体手順書」は、DX推進の全プロセスを具体的に示すものです。業務分析から施策導入、評価まで一連の流れが体系的にまとめられており、推進リーダーや外部ベンダーとの役割分担も明記されています。内容がやや専門的なので、庁内での勉強会や委託先との共有により理解度を高めることが大切です。
3. DX推進体制の構築
自治体DXの実現には、明確な体制づくりとリーダーシップの発揮が不可欠です。制度や技術を活用するだけでなく、組織内で「誰が、どのように」DXを進めるのかという仕組みが整っていなければ、DXは絵に描いた餅で終わってしまいます。
3-1 自治体内での推進組織・担当者の配置方法
まずはDXを専門に扱う組織やチームを設置しましょう。中規模自治体の場合、情報政策課や総務部門にDX専任担当者を設け、全庁に横串を通す役割を担わせる体制が一般的です。一部の先進自治体では「DXセンター」や「スマート化推進室」といった組織が立ち上がり、職員が専門特化して取り組んでいます。現場部門との連携が必須ですので、各課の代表者を交えた「プロジェクト会議体」も併設すると効果的です。
3-2 組織をまたぐ連携とリーダーシップの役割
DXは一部署だけで進めるものではありません。総務、福祉、教育、税務など多岐にわたる部門をつなげるには、強力なリーダーシップと「組織を超えた連携体制」が求められます。自治体では課をまたぐ文化が弱いため、推進役には「調整力」や「巻き込み力」がある職員が理想です。また、首長や副市長レベルが旗振り役を務め、庁内の意識統一を図ることも重要なポイントです。
3-3 専門人材(CIO/CDOなど)の活用
DX推進には、情報技術に精通した専門人材が不可欠です。民間でよく耳にするCIO(Chief Information Officer/情報統括責任者)やCDO(Chief Digital Officer/デジタル戦略責任者)といったポストを自治体でも整備し、IT戦略を中長期的に主導するようにしましょう。実際に中規模自治体でも、民間出身者を「デジタルアドバイザー」として迎える動きが強まっており、経験豊富な外部人材と内部職員の知見を掛け合わせる体制が注目されています。
4. DXの優先施策と実践モデル
限られた予算と人員の中で何から優先するかは各自治体共通の悩みです。ここでは、特に取り組みやすく、住民の満足度向上や業務効率化につながりやすいモデル施策を紹介します。
4-1 窓口業務のオンライン化
住民からの申請手続きの多くは、これまで窓口で紙の書類を提出する形が主流でした。しかし、ネットを活用した申請フォームや、マイナンバーと連携した手続きを整備することで、住民は自宅からスムーズに手続きができるようになります。また、窓口職員の応対時間が減り、職場の負担軽減にもつながります。「オンライン市役所」や「電子申請ポータル」などの構築には、段階的な導入と住民向けの周知活動が重要です。
4-2 書類のペーパーレス・電子化推進
紙の文書で行っていた内部業務も、大幅に見直すチャンスです。公文書の電子決裁システムの導入や、PDF形式の保存ルール整備などにより物理的書類を減らせば、保管スペースの縮小や職員の検索・編集作業の効率化が図れます。ただし、法的保存の要件に注意し、システム上での改ざん防止機能やバックアップ体制の整備が併せて必要です。
4-3 AI・RPAの導入事例と効果
AI(人工知能)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)といった技術を活用することで、単純作業や定型業務を自動化できます。例えば、住民からのよくある問い合わせにAIチャットボットが対応したり、月末のデータ集計をRPAが代行したりといった導入事例が増えています。中規模自治体でも、段階的なスモールスタートで導入している例があり、費用対効果を見ながら拡大が可能です。
5. 他自治体の先進事例から学ぶ
自分たちだけで一から計画するのではなく、他の自治体の成功事例を参考にすることでリスクを減らし、効果を最大化できます。ここではスケールの異なる2つの自治体の事例から、共通する工夫と着眼点を解説します。
5-1 成功事例①:小規模自治体での効率化
ある地方の人口2万人未満の町では、職員数の少なさをカバーするため、RPAによる内部処理の自動化を進めました。住民異動届の入力や公共料金の確認作業、定例レポートの自動作成などをRPAに任せたことで、年間の労働時間が約800時間削減されたといいます。スモールスタートでITの導入効果を実証し、その成果をもとに地域内の他部署へも波及させました。
5-2 成功事例②:大都市によるデジタル行政改革
政令指定都市では、全庁的に「行政手続きのオンライン化」に取り組み、100を超える手続きをインターネットに対応させました。また町の粗大ごみ回収や保育園の申し込みもスマートフォンから完結できるようにし、市民の利便性が格段に上がったという声が寄せられました。庁内にはDX推進室とシステム設計部門が連携・協議する常設の会議体があり、技術と政策が連動して動いています。
5-3 共通基盤とローカル性のバランス
全国一律の基準やインフラ(共通基盤)に依存しすぎず、それぞれの地域の事情や住民の特性を活かすローカル性のバランスも必要です。地域特有の事情を把握した職員の視点を大切にしながら、国が提供する標準的なシステムや支援制度を「自分たちに合った形」にローカライズ(地域化)して使いこなすことが、成功への近道といえるでしょう。
6. 住民視点で考えるDX
自治体DXの目的は、ただ内部業務を効率化するだけではありません。最終的に目指すのは、住民一人ひとりが「便利になった」「わかりやすくなった」と感じられるような行政サービスの提供です。つまり、住民目線の設計が運用定着の鍵を握っています。
6-1 住民ニーズに基づいたサービスデザイン
申請の電子化やチャットボット導入などの取り組みは、必ずしもすべての住民にとって使いやすいとは限りません。年齢や生活環境によって利便性は異なるため、住民の利用状況や困りごとを事前に把握し、その声を基に「サービスの設計」を行うことが重要です。例えば、高齢者向けには音声ナビ付きのオンライン申請、子育て世帯にはスマートフォンで完結可能な育児支援情報の配信など、対象に応じた対応が求められます。
6-2 デジタル・ディバイド対策
デジタル・ディバイドとは、インターネットやデジタルサービスへのアクセス環境に恵まれないことによって情報格差が生まれる現象のことです。地域や年齢による格差を放置すれば、DXの恩恵が行き渡らなくなります。そのため、タブレット端末の貸し出し、地元の公民館や図書館でのICT講習、紙ベースとの併用運用といった工夫が必要です。特定の世代や地域を取り残さない設計思想が、持続可能なDXを支えます。
6-3 利用者目線でのUI/UX改善策
UI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザーエクスペリエンス)は、行政システムが住民にとってどれだけ使いやすいかを示す重要な要素です。画面表示が分かりにくい、ボタンの配置が複雑すぎる、といったトラブルは、結果的に窓口への問合せ増加を招いてしまいます。解決のポイントは「実際に使ってもらいながら改善すること」。住民や庁内職員の声を反映して画面設計を何度もブラッシュアップすることがUI/UX向上の近道です。
7. セキュリティ・プライバシー対策
DXで扱う情報は業務の効率化だけでなく、住民の個人情報や重要な行政データが含まれるため、セキュリティ対策は避けて通れません。安全性が担保されていなければ、住民の信頼を損なってしまいます。
7-1 自治体業務における情報セキュリティの現状と課題
近年、国内外で自治体を狙った情報漏えいやシステム攻撃が増加しています。情報セキュリティ対策が不十分なままDXを進めてしまうと、個人情報の漏えいや業務停止といった大きなダメージを受ける恐れがあります。現状、自治体では基本的なウイルス対策やアクセス権限の管理に差があり、IT担当の人材が不足しているケースも少なくありません。このギャップを埋めることが急務です。
7-2 個人情報保護とクラウド活用の両立
システムをクラウド環境へ移行することで、保守管理の効率化やコスト削減が期待できます。しかし、外部のインフラに止めることに不安を感じる職員・住民の声もあるでしょう。そのため、データの暗号化や匿名化(個人を特定できない状態)を施した運用方針を策定し、クラウド事業者と連携した安全な運用ルールを策定することが重要です。ガイドラインを参考に、住民説明会で丁寧に伝える姿勢が信頼性向上につながります。
7-3 サイバー攻撃への対応と演習
標的型攻撃やランサムウェア(システムを人質に金銭を要求するウイルス)など、サイバー攻撃は多様化・高度化しています。被害を最小限にとどめるためには、職員一人一人のセキュリティ意識の向上と、実際に攻撃を想定した訓練(サイバー演習)の実施が効果を発揮します。模擬攻撃シナリオに基づいて、どのように初動対応するかを庁内外でシミュレーションしておきましょう。
8. 財源・予算確保と国の支援制度
DXの推進には、設備投資や人材育成などに対して相応の予算が必要です。資源が限られる中で、どのように予算を確保し、国の支援制度を活用していくかがポイントです。
8-1 DX投資のための予算計画
DXに必要な予算は、システム更新費、クラウド利用料、職員研修費、外部ベンダー支援費など多岐にわたります。そのため、年度単位の単発予算ではなく、中長期のDXマスタープランを策定し、複数年にまたがって段階的に予算を計上することが理想です。また、他部署と共同で予算を組む「横断的予算計画」も効果的です。
8-2 総務省や他省庁による補助金・支援事業
総務省やデジタル庁をはじめとした各府省では、自治体を対象としたDX支援メニューを公開しています。具体例としては「地域情報化推進費補助金」「自治体DX補助金」「業務改善モデル構築支援事業」などがあります。それぞれ対象経費や支援率が異なるため、担当者は申請要領をしっかり読み込み、積極的に応募することが推奨されます。
8-3 公民連携(PPP/PFI)による資金調達例
DXの推進には民間事業者のノウハウや資金を活用した公民連携も一つの方法です。PPP(Public Private Partnership)やPFI(Private Finance Initiative)は、民間主導でICTインフラを整備したり、住民課窓口のDX化を運営支援したりする手法として注目されています。民間に業務を委託するだけでなく、共にサービスの質の向上に責任を持つ協働体制が必要です。
9. DX推進における課題とその打開策
実務としてDXを推進するなかで、多くの自治体が直面しているのが「抵抗と混乱」です。ここでは、その代表的な課題と具体的な解決策を整理します。
9-1 職員の意識改革とデジタルリテラシー向上
長年、紙ベースや従来通りの業務を行っていた職員にとって、新しいやり方への抵抗感は極めて自然なものです。このため、単に「やれ」と命じるのではなく、DXの目的や意義をしっかり共有し、段階的にデジタル技能を習得してもらう研修が必要です。例えば「文書管理の電子化体験」「RPAハンズオン研修」など、実務に即した体験型の学びが効果的です。
9-2 システム・業務の標準化とその難しさ
自治体ごとに異なる業務フローや書類様式があるため、標準化や共通化を進めることにはハードルがあります。しかし、全国統一のシステム(LGWAN、標準化対象17業務など)を取り入れることで、業務ごとのバラつきを減らし、人員や予算の活用をより効率的にできます。困難が伴う分だけ、効果も大きい取り組みです。
9-3 レガシーシステムからの脱却
旧来のレガシーシステム(古くなったコンピューター環境)は、パッチ対応や保守更新だけで予算が膨らみ、DX推進の妨げになっています。これを機に一度業務全体を見直し、不要なシステムの廃棄、再構築への計画を立てることが重要です。完全な移行ではなく「段階的に新旧移行する」ことで職員の負担も減り、理解が深まります。
10. 自治体DXのこれから
DXは一過性の取り組みではなく、持続可能な自治体経営の基盤となる動きです。変化が速い技術社会においては、継続的な進化が求められます。
10-1 2025年・2030年へ向けたロードマップ
政府が進める自治体システム標準化における「2025年の崖」問題とは、2025年度末までに基幹系17業務のシステムを共通化しなければ、保守等の多大なコストやリスクが生じるという課題です。このロードマップを意識し、自団体のスケジュールを可視化し、都度関係者を巻き込んで進行管理を行いましょう。また、2030年に向けては、AIやWeb3といった新技術への対応も視野に入れる必要があります。
10-2 持続可能な行政運営の実現に向けて
最終的に自治体DXが目指すのは、限られた職員と財源でより多くの行政サービスを持続的に提供できる仕組みづくりです。現場起点のアイデアやデータ活用を積極的に取り入れ、地域住民とともに未来型行政を築いていく姿勢がカギとなります。
10-3 新技術(Web3、マイナポータル等)への対応と将来展望
Web3(ブロックチェーン技術を基盤とした新しいインターネットの形)やマイナポータル(行政とのやり取りをインターネットで完結させる個人用ページ)など、今後の行政サービスには新たな技術導入も不可避です。これらはまだ発展途上であり、すぐの導入が難しいこともありますが、「まずは学ぶ」「試行から始める」姿勢が未来につながります。

 dx
dx