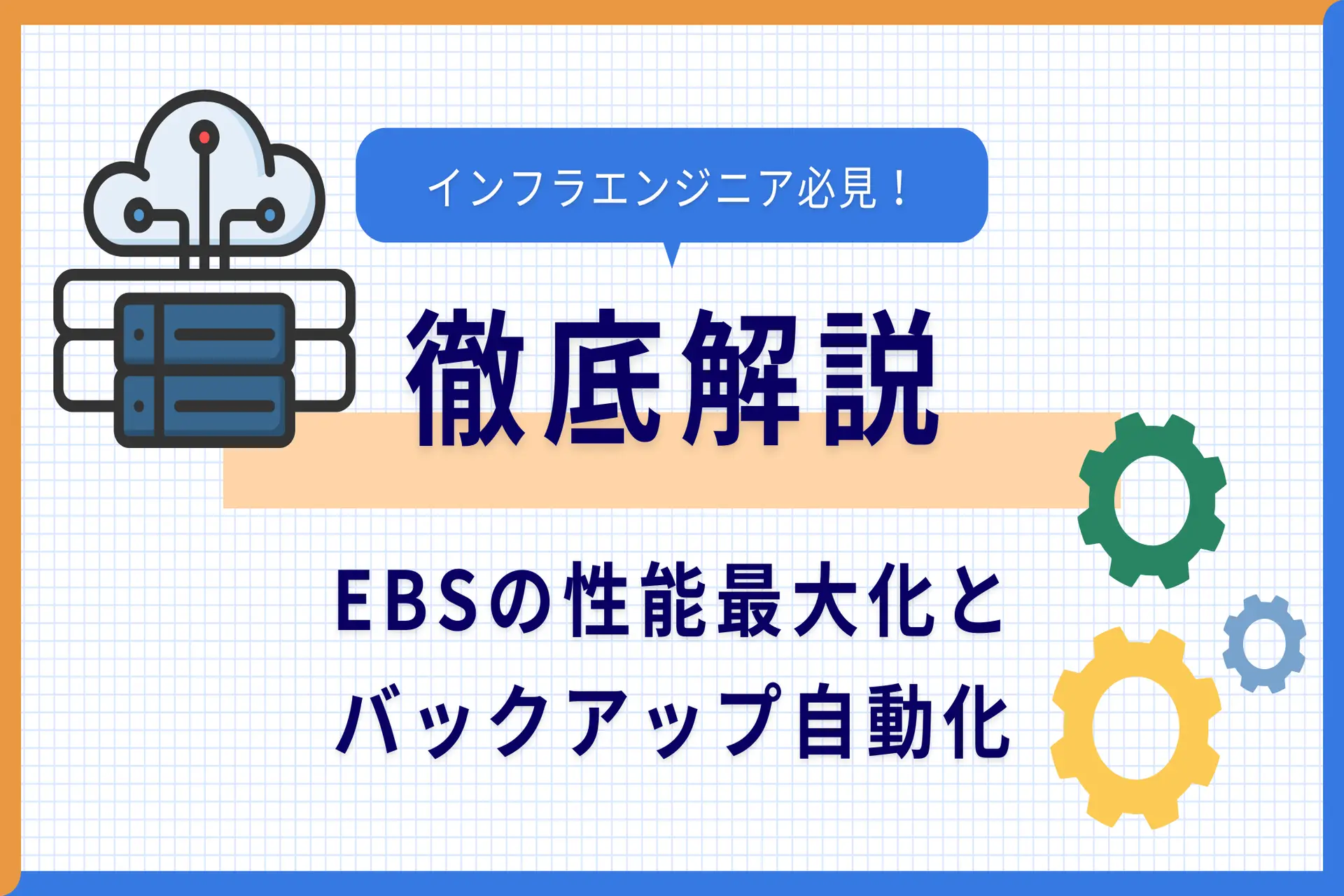DX推進にひそむ5大リスクとは?セキュリティ、法令対応から人材育成まで徹底解説
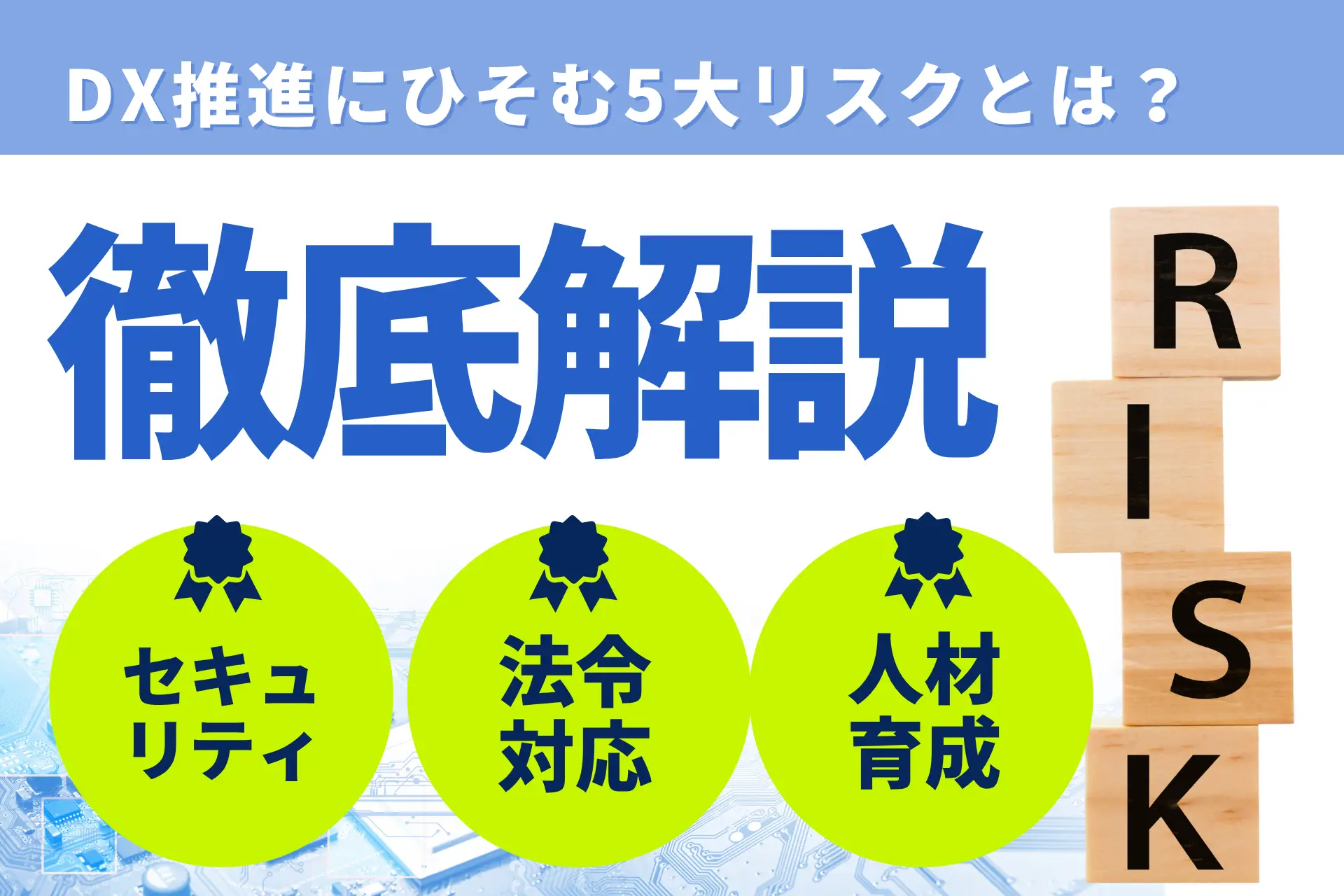
目次
1. DX推進によって生じる主なリスクとは
DXは企業にとって大きな可能性を秘めた取り組みですが、戦略なしに進めてしまうと、さまざまなリスクに直面する恐れがあります。
ここでは、特に多くの企業がつまずきやすい5種類の主なリスクについて解説します。
1-1 セキュリティリスク
IT技術を使って企業活動を支えるということは、その分だけサイバー攻撃や情報流出などの脅威にさらされるということです。
DXの一環としてクラウドサービスや外部サーバを活用する企業が増える中、セキュリティ対策が十分でなければ、ささいな設定ミスやパスワード漏洩から重大な事故につながる危険があります。
例えば、一つのシステムがサイバー攻撃を受けたことで、社内全体や取引先まで影響が広がった例もあり、セキュリティはDXを支える不可欠な土台です。
1-2 データのガバナンスと漏洩の危険
「ガバナンス」とは、企業が保有するデータを適切に管理・統制するためのルールや枠組みのことです。
DXを推進する中で多くの企業が大量のデータを集めて活用していますが、扱う責任を十分に意識せずに運用してしまうと、「誰がどの情報にアクセスできるか」というルールが曖昧なままになりがちです。
その結果、内部からの漏洩事故や第三者による不正アクセスが発生するリスクが高まります。
1-3 法的・コンプライアンス上のリスク
DXにおいてデータを扱う際は、個人情報保護法や知的財産関連法など、さまざまな法律に注意する必要があります。
特に、海外と取引がある場合は、ヨーロッパの「GDPR」といった厳格な規制にも対応しなければなりません。
これらへの対応を怠ると、社会的な信頼を失うだけでなく、多額の罰金や賠償責任が発生する可能性もあるため、リスクとして無視できません。
1-4 オペレーションリスクとレガシーシステムの問題
社内に古くからある業務システム(レガシーシステム)がDXに適していないケースもあります。
新しい技術と古いシステムを無理やり連携しようとして、システムの不具合が起きることも多く見られます。
また、業務プロセスが人によって進め方に差がある場合、その属人性がDXによる統一化の足かせになることもあります。
1-5 組織文化・人材の変革に伴うリスク
新たなテクノロジーを導入しても、それを使いこなす人や体制が整っていなければ、本当の意味でのDXは実現できません。
特に、これまでの業務のやり方に慣れた社員が変化を拒んでしまうこともあり、「DX推進=単純な技術導入」ではないことがうかがえます。
組織文化と人材の変革にも目を向けることが重要です。
2. DXにおける情報セキュリティの課題
DXの推進において避けて通れないのが、情報セキュリティへの対策です。
デジタル環境では、データや重要な業務システムがインターネットと常時つながっています。つまり、この便利さの裏には、常に不正アクセスやサイバー攻撃の脅威が潜んでいるということを意味します。
ここでは、近年多くの企業で問題となっている3つのセキュリティ課題を取り上げ、その対応策について考えていきましょう。
2-1 増大するサイバー攻撃への対応
サイバー攻撃とは、インターネットを通じて企業のシステムやネットワークに不正侵入したり、ウイルスを送り込んだりして、情報を盗んだり壊したりする行為を指します。
昨今では、個人を狙った詐欺メール形式の「フィッシング」攻撃や、企業のシステムへ侵入しデータを勝手に暗号化して身代金を要求する「ランサムウェア」が急増しています。
これらの手口は年々巧妙化しており、単なるウイルス対策ソフトだけでは防ぎきれないケースもあります。
したがって、社内で発見能力を高めるなど、複合的なセキュリティ対策の導入が不可欠です。
2-2 クラウド移行による新たなリスク
企業が基幹システムや業務データをクラウド(インターネット上のサーバー)に移行する流れは加速しています。
この背景には、コスト削減や働き方改革、BCP(事業継続計画)の観点があり非常に合理的です。
しかし、クラウドサービスでは管理の一部を外部に任せるため、自社ですべてをコントロールできないというリスクも抱えています。例えば、クラウド提供会社のトラブルや障害が、自社の業務停止に直結する場合もあるのです。
そのため、クラウドの選定段階から「どこにデータが保管され、誰がアクセスできるのか」といった視点で、可視性とセキュリティを重視する必要があります。
2-3 インサイダーリスクとゼロトラストモデルの重要性
「インサイダーリスク」とは、内部の人間がうっかり操作ミスをしたり、悪意を持ってデータを持ち出したりといった、企業内部から起こる情報漏洩のことです。
実は情報漏洩の約半数が、外部からの攻撃ではなく、このインサイダーリスクに起因していると言われています。
このような背景から注目されているのが、「ゼロトラスト・セキュリティモデル」です。
これは「会社のネットワーク内=安全」という前提を捨て、社内のすべてのアクセスに疑いの目を向け、必要な人だけに必要な範囲で許可を与える方式です。
DXを行う企業では、このような最新のセキュリティモデルを取り入れることで、インサイダーのリスクを最小限に抑えることができます。
3. データの取り扱いとプライバシーリスク
DXの核心とも言えるのが「データの利活用」です。
企業が顧客のニーズを読み取り、ビジネス戦略を変革していくうえで、データの分析は欠かせません。
一方で、データの活用には常に「プライバシー保護」や「倫理的配慮」が付きまとい、これを軽視すると社会的信用を失うリスクにもなりかねません。
この章では、データ時代に必要な視点や注意点について考察していきます。
3-1 個人情報保護と国内外の法規制(GDPRなど)
個人情報を取り扱う場合、企業は必ず関連法令を守る必要があります。
日本国内では「個人情報保護法」が定められており、2022年の改正により、違反に対する罰則が厳格化されています。
さらに海外市場とも取引のある企業にとっては、EUが施行する「GDPR(一般データ保護規則)」への対応も不可欠です。
GDPRでは、利用者の同意取得や処理目的の明示などが求められており、違反すると最大で2,000万ユーロ、または年商の4%の制裁金が科されることがあります。
コンプライアンス(法令順守)は、単なるチェックリストではなく「企業の社会的信頼を維持するための土台」であり、DX戦略と並行して進める必要があります。
3-2 データのライフサイクルマネジメント
データには「取得」から「保存」「活用」「廃棄」まで、明確なライフサイクル(データの一生)があります。
企業はこのサイクル全体を見通して、一貫性のある管理を行わなければなりません。
特に注意が必要なのは、「データをいつまで保存するか」「削除の証拠をどのように残すか」といった終末管理の部分です。
不必要なデータをだらだら保管しておくと、流出時の影響が大きくなるほか、クラウドの容量を圧迫してしまうなど、業務効率の低下にもつながります。
DXを推進するうえで、データ管理はIT部門だけでなく、業務部門とも連携して取り組むべきテーマです。
3-3 顧客データ活用と倫理的な配慮
企業がデジタルマーケティングやパーソナライズサービスに顧客データを活用する場面が増えています。
例えば、購入履歴にもとづいたおすすめ商品の提示は、便利で顧客満足を高める取り組みです。
しかし同時に、「どこまでのデータ分析が許容されるのか」という倫理的な側面も忘れてはなりません。
過剰に顧客の行動や嗜好を分析しすぎると、「監視されているようで不快だ」と受け取られる可能性があります。
企業は便利さと倫理性のバランスを取りながら、ユーザーに安心感を与えるデータ活用を目指すべきです。
4. DX戦略とリスクマネジメントの統合
DX推進において重要なのは、リスクを後追いで処理するのではなく、「戦略策定の初期段階からリスクマネジメント視点を組み込む」ことにあります。
つまり、DXは単なるシステム導入や業務改革ではなく、組織経営そのものの構造変革を伴う以上、リスク管理も含めた包括的な戦略が必要です。
ここでは、その統合を実現するための基本的な考え方と実行ステップを解説します。
4-1 リスクアセスメントの実施方法
「リスクアセスメント」とは、事業活動の中でどのようなリスクがあり、それが生じた場合にどれほどの影響を与えるかを見極めるプロセスのことです。
企業によって導入しているIT環境も業務範囲も異なるため、画一的ではなく、自社に合ったリスクの洗い出しが求められます。
実施手順としては、以下がベースとなります:
① 想定されるリスクの洗い出し
② 各リスクの発生可能性と影響度のスコア化
③ 優先的に対応すべきリスクの特定
この手順を経ることで、計画段階から「どの分野にどれだけのリソースを振り分けるべきか」が明確になります。
4-2 リスク対応戦略(回避、軽減、受容、移転)
リスクへの対応には大きく4つの方針があります。
それぞれのリスクの性質に応じて、適切に選ぶことが求められます。
- 回避(Avoid):リスクの原因となる活動自体を中止したり、取り除くことで発生を防ぐ。
- 軽減(Mitigate):リスクが発生しても影響を小さく抑える手段を構築する(例:セキュリティ強化)
- 受容(Accept):リスクの影響が軽微な場合、自社で許容範囲内として受け入れる対応
- 移転(Transfer):保険や外部委託などにより、リスクの影響を他者に転嫁する
戦略的にこれらを使い分けることで、リスクへの対応力は飛躍的に高まります。
4-3 ビジネスインパクト分析(BIA)の導入
「ビジネスインパクト分析(BIA)」は、あるリスクが実際に発生したと仮定した際に、自社の業務やサービスにどの程度の影響が出るかを定量・定性的に把握する手法です。
例えば、DXによって集中管理されるようになった在庫システムが停止すれば、顧客納期の遅延や収益の損失が発生するかもしれません。
そのような影響範囲を事前に見積もることで、適切なバックアップ策や優先的に守るべき重点ポイントが明らかになります。
4-4 仮想演習やBCPとの連携
実際のリスクに備えるには、「仮想演習(シミュレーション)」を行うことも効果的です。
例えば、「もしファイルサーバーがサイバー攻撃を受けて丸1日使えなくなったらどうするか?」という想定の下、部門の連携・復旧フロー・役割分担などを確認しておくのです。
さらにBCP(事業継続計画)と組み合わせることで、災害やシステム障害など突発的な事態に対する組織の回復力強化が図れます。
5. デジタルリスクマネジメントのフレームワーク
リスク対策は独自の取り組みだけでは不十分な場合もあります。
そこで役立つのが、国際的に認められた「標準フレームワーク」の導入です。
これにより、社内外での共通認識が得られ、第三者評価や監査にも活かすことができます。
5-1 NIST、ISO/IEC 27001などの国際標準
「NIST(米国国立標準技術研究所)」が発行するサイバーセキュリティフレームワーク(CSF)は、主に5つの活動カテゴリに分かれています:
① Identify(識別)
② Protect(防御)
③ Detect(探知)
④ Respond(対応)
⑤ Recover(回復)
また、情報セキュリティのマネジメントを体系化した「ISO/IEC 27001」は、企業が情報セキュリティ管理を行う際の国際的なガイドラインです。
これらを一部参照するだけでも、リスク管理体制の精度は高まります。
5-2 CISO(最高情報セキュリティ責任者)の役割
CISOとは、Chief Information Security Officerの略で、企業内で情報セキュリティ全般を統括する役職のことです。
この役割には、単にセキュリティ対策を強化するだけでなく、経営陣と連携し、ビジネスに直結するセキュリティ投資の判断も求められます。
CISOが存在することで、「誰がセキュリティの責任者か」が社内で明確になり、迅速な対応が可能になります。
5-3 継続的モニタリングとリスクダッシュボードの活用
DXが進むとシステムの数や連携範囲が広がり、それに比例してリスクの監視対象も増えていきます。
これを管理するには、「リスクダッシュボード」や「モニタリングツール」の活用が有効です。
リアルタイムでシステム状況や障害・異常検知を可視化できる仕組みがあれば、担当者は速やかに対処判断ができます。
継続的監視は、リスクを「予防」する上でも大きな意味を持つのです。
6. DXに必要な人材・組織体制とリスク管理力
どれほど優れた計画や対策を練っても、それを支える人材や組織が不十分であれば実効性は伴いません。
特にDXによる業務変革は、IT部門だけでは完結せず、全社的な体制づくりと継続的なスキルアップが求められます。
ここでは、人材と組織面から見たリスク管理体制のあり方を紹介します。
6-1 DX推進人材とセキュリティ専門家の確保
DXを成功させるためには、テクノロジーだけを理解する人材でなく、「業務とITの両面をつなげる力」を持った人材が重要です。
一方、サイバーリスクや法律面の課題に対応するには、セキュリティやコンプライアンスに精通した専門家が欠かせません。
中には外部ベンダーや専門コンサルタントとの協業を通じて、不足しているスキルセットを補完する企業も増えています。
理想は、社内における「技術」「業務」「リスク」の橋渡しができる人材を育成し、常に進化し続ける体制です。
6-2 クロスファンクショナルな体制づくり
DXでは多くの部門・部署が関与します。
だからこそ、部門横断的な体制(クロスファンクショナルチーム)を構築し、一貫したビジョンのもとにリスク対策を連携させることが大切です。
この体制をつくることで、セキュリティは特定部門の責任ではなく「全社共通の課題である」との意識が醸成されます。
例えば、月に1度、ITと経営企画、法務などの部門が集まり、リスク共有のためのミーティングを行うだけでも、連携の質は変わります。
6-3 従業員教育とセキュリティ意識の向上
最終的な情報漏洩の原因の多くは、ヒューマンエラーや誤操作です。
これはどれほど技術的な対策を講じても「人の意識」が低ければ防ぎようがありません。
そのため、組織全体として「セキュリティ教育」「意識向上活動(例:eラーニング、フィッシングメール訓練など)」を定期的に行うことが推奨されます。
特に現場でシステムを使う社員には、「その操作がどんなリスクにつながるか」を直感的に理解してもらえるような内容にすると効果的です。
7. 実際のトラブル事例から学ぶDXリスク
リスクの重要性を認識していても、「実際に何が起こるのか」がイメージできなければ対策はおろそかになりがちです。
そこで参考になるのが、DXの過程で国内外の企業が経験したトラブル事例です。
ここでは、2つの特徴的な失敗例を取り上げ、それぞれの教訓と再発防止のためのポイントを解説します。
7-1 国内外のデータ漏洩・障害事例
【事例①:大手企業のクラウド移行による顧客情報の流出】
ある国内大手企業は、業務の効率化を目的に社内システムをクラウドに一括移行しました。
ところが、アクセス制御の設定が不十分だったため、本来閲覧できない関係者以外の社員からも機密情報が参照可能な状態に。
数万件にのぼる顧客情報が流出し、企業ブランドの信用は大きく損なわれました。
この事例が示すのは「クラウド化=安全」ではないということです。
【事例②:海外企業のゼロデイ攻撃による生産ライン停止】
ある製造業のグローバル企業では、ランサムウェアによるゼロデイ攻撃(パッチが未提供の脆弱性を突く攻撃)により、工場の生産ラインが48時間にわたり完全に停止。
損害額は数十億円にも達しました。
このトラブルは、「OT(Operational Technology:工場設備など)とITがつながるDX時代」におけるセキュリティ観点の盲点を突かれた事例でもあります。
7-2 失敗から読み解く教訓と再発防止策
上記2つの事例から導き出せる教訓は以下です。
① 技術任せではなく「人とプロセス」の設計が不可欠
② 重要情報へのアクセス管理は最小限に制限する
③ テストや検証、仮想演習を通じた事前評価が求められる
④ 「ITだけ」ではなく「業務プロセス」「経営視点」にまたがったリスク統制が重要
再発防止のためには、実際の事例を社内で共有し、自社に置き換えて考えられる「仕組み化」と「風土づくり」がカギを握ります。
8. 今後のデジタルリスクの変化と対応戦略
DXは今後さらに深化し、その姿は一層多様になります。
つまり、今後のリスクもより複雑化、かつ予見しづらいものになる可能性が高いのです。
そこで注目すべきは、「未来に向けてのリスク対応力」です。
8-1 AI・IoT導入がもたらす新たなリスク
AIやIoTなどの高度技術が普及することで、人力では手が届かなかった分野にまで自動化の波が押し寄せています。
例えば、製造現場で多く導入されているIoTセンサーがハッキングされることで、誤作動や無断操作が行われるリスクも指摘されています。
またAIについては、誤学習によって意図しない判断を下したり、学習に使うデータが偏っていることで不適切な出力をするリスクがあります。
今後は「透明なAI運用ルール」や「IoTデバイスの物理・ネット両方のセキュリティ強化」が喫緊の課題です。
8-2 ESG・サステナビリティとの関係
企業が社会課題に取り組む姿勢として、ESGやサステナビリティの観点が重要性を増しています。
DXとESGの関係性では、情報保護の透明性や倫理的な対応が問われる場面が増えています。
「どのようなデータを」「どう活用して」「誰に説明責任を果たすのか」を明確にすることが、企業ブランドにも直結する時代です。
これは、単に「守るべき」ルールというより、自社の企業価値をどう表現するかという、戦略的意義があります。
8-3 中長期的なリスク管理体制の強化
未来のリスクは「今想定できる範囲」だけではありません。
そのため、短期対応だけでなく、「5年後、10年後を見据えた体制作り」が欠かせません。
例えば、:
- 定期的なリスクレビュー会議
- 自社業界に特化したリスクレポートの活用
- 若手へのリスクマネジメント教育
など、柔軟性と持続性を同時に備えたリスク管理体制を構築することが重要です。
9. まとめ:DX推進を成功させるために欠かせない“リスクとの共存”
本記事で紹介したように、DXの成功には技術だけではなく、「リスクとどう向き合うか」という視点が不可欠です。
デジタル化が進むほど、見えにくい部分での障害や不具合、倫理課題といった「新たなリスク」が常に生まれてきます。
そのときに求められるのは、技術だけに頼らず、人・組織・ガバナンスが一体となって支える「三位一体のアプローチ」です。
変化を恐れるのではなく、リスクを明文化し、共有・対応する文化さえ醸成できれば、企業は逆にそこから学びと競争力を手に入れることができます。
DXとは、挑戦であり、変革であり、学習の連続です。
ぜひ貴社におけるDX推進の一助として、この記事の内容をご活用ください。

 dx
dx