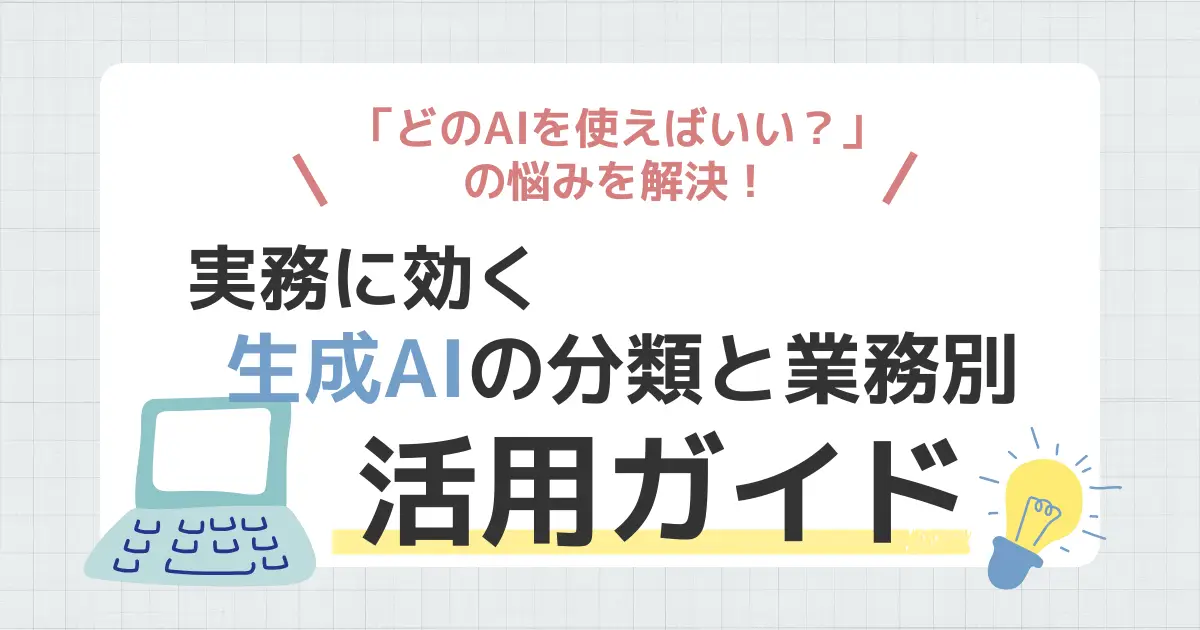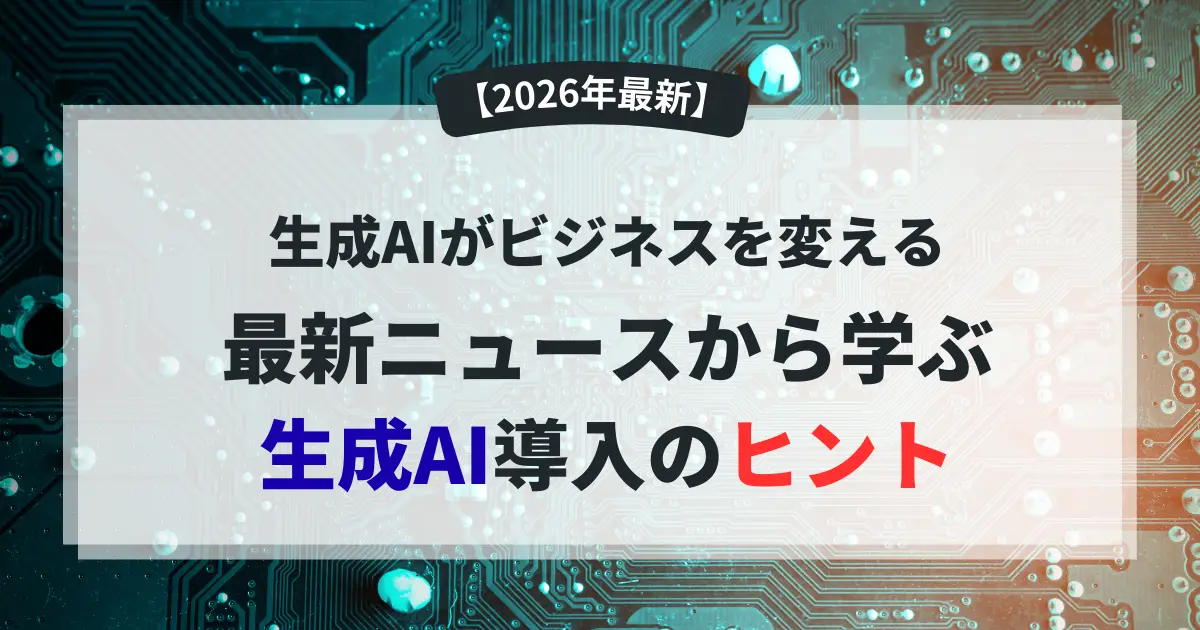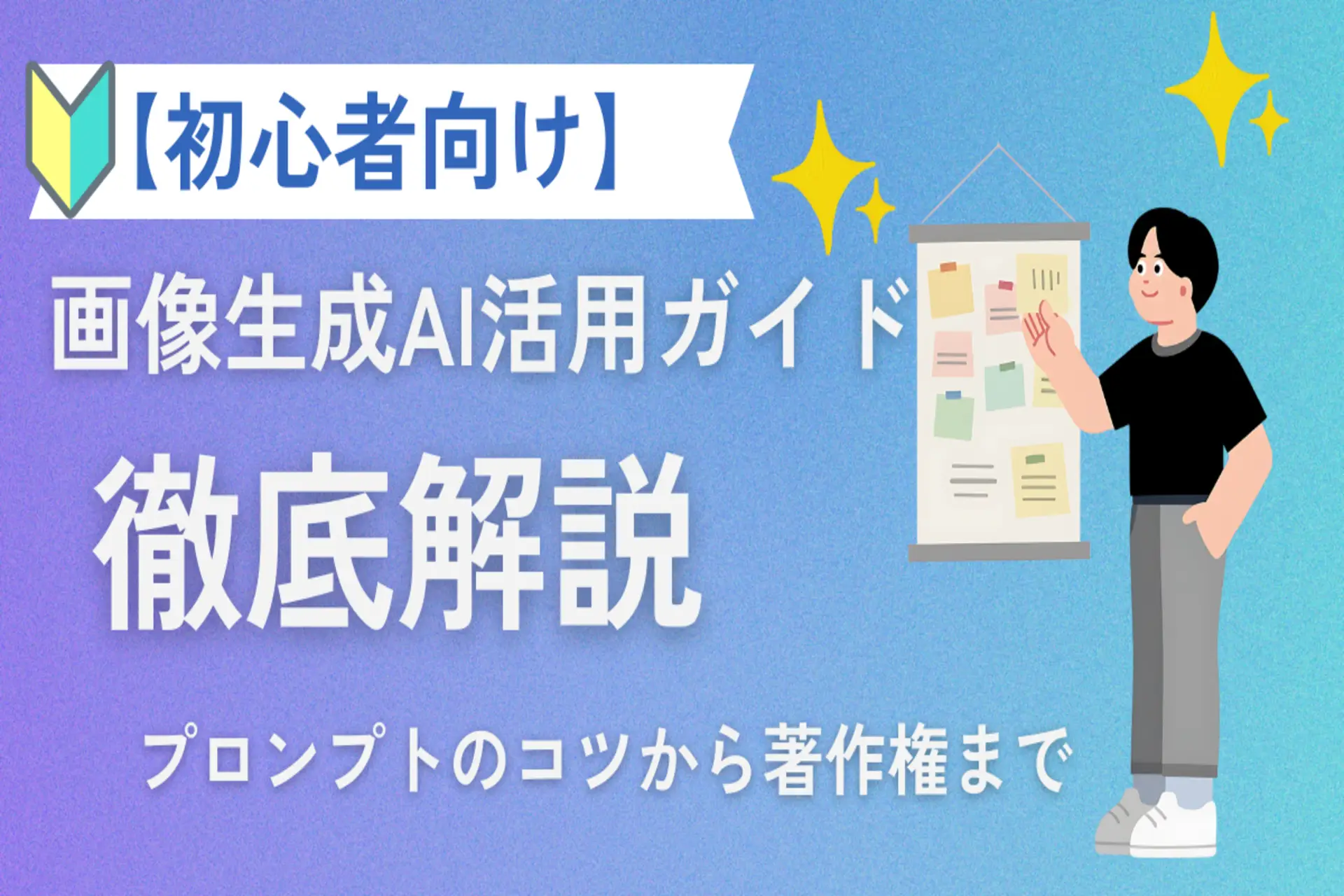DXで業務効率と生産性をアップする方法|中堅企業向け事例集
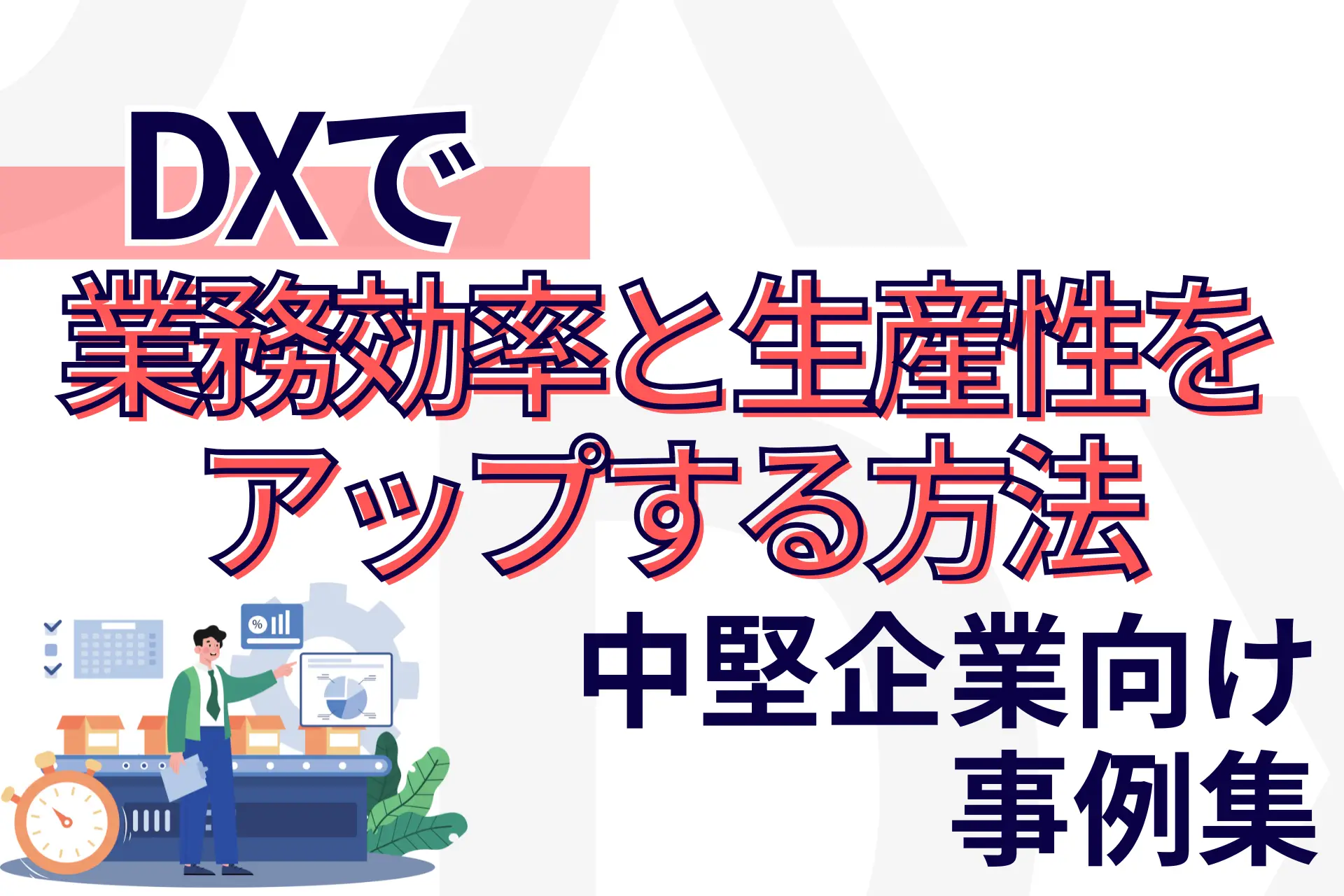
目次
1. 業務効率化が必要とされる背景
DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が、多くの企業で急務とされる理由は、単なる技術導入のブームではありません。
背景には、人口減少や労働力不足といった社会的な問題から、企業の生産性を支える基盤を変革する必要性があります。
ここでは、特に中堅企業の情報システム部門においてよく見られる課題と、その解決に向けたDXの有効性を多面的に紹介します。
1-1.人手不足・高齢化社会による影響
現在、日本全体で労働力人口の減少が続いており、特に製造業などでは人材確保が年々難しくなっています。
総務省の統計によると、65歳以上の高年齢層の割合が約30%を超えた現在、今後ますます「人がいない」「現場が回らない」といった課題が深刻化していきます。
こうした人手不足の中でも安定した業務を確保する方法として、DXの果たす役割が重要です。
具体的には、人が行っていた繰り返し作業を自動処理(RPAなど)したり、情報の一元化により管理や対応の手間を減らす仕組みが必要とされます。
1-2.働き方改革とDXの連動性
2019年に施行された「働き方改革関連法」により、企業は残業時間の抑制や柔軟な勤務形態の導入を進めるよう義務付けられています。
しかし、柔軟な働き方を取り入れるには、業務がデジタル化されていることが前提です。
いつ、どこにいても仕事ができる環境を構築するには、クラウド(インターネット上のサービス)活用や、業務の見える化が不可欠です。
その結果、DXの推進は単なるIT化ではなく、企業全体の働き方を再設計する活動としても求められています。
1-3.コスト削減と生産性向上の要求
企業の競争力を左右する要素の一つがコスト競争力です。
しかし、人件費や材料費の上昇などで、企業は利益を確保しにくくなっています。
こうした状況の中、DXの導入は業務プロセスを効率化し、必要な労力や時間を削減する手段として注目されています。
ツール導入によって、手作業でのデータ入力・確認作業を削減したり、在庫管理などを自動化することで、業務コストの低減と同時にミスの削減にもつながります。
こうした社会的・組織的な背景を踏まえ、企業が具体的にどのような施策で業務を効率化できるのかを次章以降で詳しく解説していきます。
2. DX前に見直すべき業務課題の整理
DX(デジタルトランスフォーメーション)を導入する前に見直すべきことのひとつが「今ある業務の問題点を正確に把握すること」です。
多くの企業では、長年続けてきたやり方に慣れてしまい、非効率であることやリスクを抱えていることに気付きにくくなっています。
「とりあえずDXだから何か始めよう」ではなく、自社の現状を正しく理解し、解決の優先順位をつけることが、成功への第一歩です。
2-1.ムダな業務プロセスの洗い出し
まずは、自社内の業務フローを見える形に「整理=業務棚卸し」することが重要です。
ひとつの注文に対して複数の部署が同じ情報を何度も入力していたり、承認を得るまでに紙の回覧が多段階にわたっている、といったムダな流れがあることは珍しくありません。
このような不要なステップがどこにあるのかを洗い出し、効率化するポイントを見極めましょう。
また、業務の重要度や時間・人手のかかり具合、さらにはデジタル化のしやすさなどの観点で、優先順位をつけることも大切です。
2-2.紙・Excelベースの運用の限界
FAX、紙書類、手書きの帳票、Excelファイルなど、個々人の手元で完結するアナログ管理は、情報の伝達・共有に大きな手間がかかります。
また、入力や転記のたびにミスが起きるリスクも高く、業務品質の安定化を妨げます。
特に、Excelによる運用は一見便利に見えても、「ファイルがどれか分からない」「上書きしてしまった」「担当者がいないと使えない」といった属人化の温床になることもあります。
そのため「紙・Excelから脱却できる部分はどこか?」を検討し、汎用的な業務であればシステム化の優先対象となります。
2-3.部門間の情報断絶・属人化
営業部と製造部、経理と総務など、部門が異なることで情報連携が取れず、業務の遅延や手戻りが起きることは多くの企業で見られます。
さらに、「○○さんしか分からない」「あの人のExcelがないと締め作業ができない」といった属人化は、休暇や退職時のリスクにも直結します。
DXを導入する前段階で、こうした業務知識・ノウハウが一部の人にだけ集中していないかを確認しましょう。
ノウハウの可視化やマニュアル化を進め、役割分担を明確にすることが、デジタル化へのスムーズな橋渡しとなります。
3. DX導入前の準備・体制構築
DX成功のカギは、ツール選定や技術力よりも「準備」にあります。
特に人・理念・文化といった“非IT要素”が最終的な定着率を大きく左右します。
このセクションでは、中堅企業がDXを円滑に導入し、継続的に運用できる体制づくりのポイントを紹介していきます。
3-1.経営陣のコミットメントとビジョン共有
DX推進を現場任せにしてしまうと、どうしても方向性がブレてしまい、効果が薄くなります。
そのため、経営陣自らが「なぜDXを行なうのか」「どうなりたいのか」というビジョンを明確にし、全社に共有することが不可欠です。
言い換えると、経営と現場の“つなぎ役”として情報システム部門が果たす役割は大きく、現場の課題や改善のヒントを上層部に届ける姿勢が求められます。
また、新しい取り組みに対して社内から抵抗が起きた場合でも、トップの支援があることで推進力を保つことができます。
3-2.推進チームの組成と人材育成
DXは一部門だけで完結する取り組みではありません。
計画から導入、運用・改善フェーズまでを見渡せる横断的な「推進チーム」をつくることが理想的です。
このチームには、現場の実務を担うスタッフだけでなく、経営企画、システム担当など、さまざまな立場のメンバーを含めることで多様な視点から課題解決を検討できます。
さらに、内部にDXの専門家が足りない場合は、外部パートナーとの連携や、IT人材のスキル向上のための研修などを進めていきます。
3-3.業務プロセスの可視化・業務棚卸し
「業務プロセスの可視化」とは、業務の流れを図や一覧にして、誰が・何を・何のために行っているのかを明らかにする作業です。
これにより、ムダな手間、重複作業、属人化などが可視化でき、改善すべきポイントや優先順位が明確になります。
一覧にしたプロセスをフローチャートにすることで、関係部門同士の連携不足や情報ロスの箇所が客観的に見えてくることもあります。
業務の棚卸しはシステム導入の前提条件であり、ここでの抜け漏れが後々のDXの成功可否に大きく影響するのです。
4. DXによる業務効率化の具体的アプローチ
ここまでの準備が整った段階で、いよいよ実際のDX施策へと移行します。
とはいえ、DXに使える技術や手法は多種多様であり、何をどの順序で使うべきか迷ってしまうことも。
このセクションでは、具体的なアプローチ別にわかりやすく紹介し、自社に取り入れる際の参考になるよう整理していきます。
4-1.業務自動化(RPA、BPM)の導入
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、定型的な手作業をソフトウェアロボットが自動で行ってくれる仕組みです。
毎月の請求書作成やデータ集計など、ルール通りの繰り返し作業を短時間かつミスなく処理できます。
一方、BPM(ビジネス・プロセス・マネジメント)は、業務全体の流れ(ワークフロー)を最適化する仕組みであり、RPAとは異なりプロセスそのものを見直して改善する方向性です。
この2つを組み合わせることで、「無駄を省く」「作業を代替させる」といった多角的な効率化が実現できます。
4-2.業務の可視化と分析(BIツールなど)
BI(ビジネスインテリジェンス)ツールとは、企業のデータを見やすく「見える化」して、現場の意思決定を助ける分析ツールです。
「売上の傾向は?」「どの工程がボトルネックになっている?」といった問いに対して、グラフやダッシュボードで直感的に把握できます。
また、リアルタイムのデータから変動に即応できたり、部門ごとの数値を比較して取り組みの成果を可視化するなど、「気付き」を得るための有用な手段になります。
複雑なコーディング不要で使える製品も多く、Excelに頼っていた集計業務や会議資料の作成をより効率化できます。
4-3.クラウド活用とシステム統合
クラウドとは、インターネット上で使えるサーバーやアプリケーションのことです。
これを利用することで、PC1台あればどこからでも社内システムにアクセスできる環境を構築でき、在宅勤務や出張先からの対応もスムーズになります。
また、販売管理や勤怠管理など部門ごとにバラバラだったシステムを1つのプラットフォームに統合すれば、情報の一元管理により重複入力やミスが防げます。
クラウド化は運用・保守の手間やコストも最小限に抑えられる点で、中堅企業にもメリットが大きい手法です。
4-4.ノーコード/ローコード開発の活用
従来の「システム開発」は、IT専門の技術者が多くのコード(プログラム)を使って行うものでした。
しかし、近年ではプログラミング不要の「ノーコード」や、最低限のコード入力で操作できる「ローコード」ツールが登場し、業務の現場担当者でも手軽にアプリを作れるようになっています。
具体的には、「申請フォームの作成」「社内ポータルの構築」「チェックリストのデジタル化」など、日常業務にすぐ役立つ仕組みを自社で素早く構築可能です。
このような開発スタイルは、スピード感のある業務改善や現場での運用定着を後押しします。
5. 業種別のDX成功事例紹介
業種や業態によって、DXの進め方は異なります。
ここでは、代表的な4つの業種に関して成功しているDX活用事例を紹介します。
ここで紹介する実例をもとに、自社の課題解決につながるヒントを得てください。
5-1.製造業:スマートファクトリーでの自動化事例
ある製造会社では、「スマートファクトリー」と呼ばれるDX環境を工場に導入しました。
この取り組みでは、センサーやIoT(Internet of Things=機器のインターネット接続)を活用して、工場内の機械の稼働状況や生産効率をリアルタイムにモニタリングできるようにしました。
結果として、人手に頼っていた記録や管理作業が不要になり、生産設備の保守タイミングも予測可能となり、ダウンタイム(稼働停止時間)を削減することに成功しました。
5-2.小売業:在庫・発注業務のデジタル化
中堅規模の小売業者では、在庫の過不足や発注ミスが慢性的に発生していました。
そこで、販売履歴や天候、曜日などのデータをもとにした需要予測AIツールを導入し、仕入れタイミングと数量を自動判定できる仕組みに刷新しました。
その結果、売れ残りや欠品が大幅に減少し、業績向上に結び付きました。
また、これまではベテラン担当者だけが感覚で行っていた発注業務を標準化でき、新人スタッフでも対応できる仕組みとなりました。
5-3.サービス業:接客対応のDX
ホテルチェーンでは、フロント業務の混雑と接客品質のばらつきが課題でした。
そこで、チェックイン用のセルフ端末・スマホ予約管理アプリ・AIによる問い合わせ対応チャットボットを導入し、業務分散とスピードアップを実現しました。
さらに、利用客の来館時間帯や要望データを分析し、最適な対応スタッフ配置をおこなう体制まで構築されました。
オペレーションが安定化し、顧客満足度の向上も図れた好例です。
5-4.官公庁・自治体:書類申請・業務プロセスの電子化事例
地方自治体では、申請書類の提出や処理に時間がかかり、市民の負担になっていました。
このため、オンラインで申請できる電子手続きシステムが構築され、職員側も確認・承認の流れをBPMとRPAでスムーズに処理できる仕組みが整いました。
結果として、対応スピードが約2倍に短縮し、業務負荷が軽減されています。
市民側、行政側、双方でのDXの恩恵が見える好事例になっています。
6. DXツール・ソリューションの選定ポイント
DXを進める上で、技術やツールの導入は避けて通れない工程です。
ただし、ツールは万能ではなく、自社の課題や業務フローに合致したものを選定しなければ、逆に効率を下げてしまうこともあります。
このセクションでは、自社に最適なDXツールを選ぶための視点と、注意すべきポイントを解説します。
6-1.自社課題にマッチした機能要件の明確化
最初にすべきことは、「なぜこのツールを導入するのか?」という目的を明確にすることです。
「紙の申請業務をデジタルにしたい」のか、「他部署とのデータ共有を効率化したい」のか、目的がぶれてしまうと導入後に「使えない」「効果が出ない」といった結果を招く恐れがあります。
また、どのような機能が必要か、入力画面の柔軟さ、承認フロー、利用人数、スマートフォン対応の有無など具体的な機能要件を整理しましょう。
自社の業務内容に即したツールであるかを、導入前にきちんと検証しておくことが大切です。
6-2.導入コスト、スケーラビリティの検討
DXツールにはさまざまな料金体系がありますが、初期費用と月額利用料、カスタマイズ費用、将来的なライセンス追加コストなど、トータルで検討する必要があります。
また、今は小さく始めても、後の拡張に対応できるか(スケーラビリティ)も重要な観点です。
IT資産は一度導入すると長く使い続けるケースが多く、後から「他の部署では使えない」「人数追加で費用が跳ね上がる」とならないよう、将来を見据えた判断が求められます。
費用対効果(コストパフォーマンス)を事前にシミュレーションした上で、導入すべきです。
6-3.サポート体制・社内定着のしやすさ
どんなに高機能なツールも、現場で活用されなければ意味がありません。
そのため、サポート体制が充実しているベンダー(提供企業)を選び、導入から操作説明、運用まで丁寧に寄り添ってくれるかを確認しましょう。
また、直感的に操作できるインターフェース、マニュアルやFAQの整備、日本語対応やセキュリティの基準なども比較ポイントになります。
「自社の従業員がスムーズに使いこなせるか?」を必ず念頭において選定しましょう。
7. 自社でのDX推進ロードマップの描き方
DXの取り組みは一度きりの導入では完結しません。
継続して運用し、改善を重ねるためには、段階的な「ロードマップ(計画表)」が必要です。
このセクションでは、DXを推し進める上で、どのような流れで計画を立て、実行していけば良いかを紹介します。
7-1.フェーズごとの目的と到達目標
DXは、初期検討→試験導入→本格展開→定着→改善という段階を踏んで進めるのが一般的です。
各フェーズで「どこまで進んだら成功か」という到達目標を設定しておくことで、成果を見える化できます。
初期段階では「紙業務を3割削減」、試験導入では「RPAで2業務を自動化」、本格展開では「全社展開までに6か月」など、明確なゴール設計が必要です。
この指標を基に、関係者と進捗を共有しやすくなります。
7-2.KPI・効果測定の指標設計
KPI(重要業績評価指標)は、DXの効果を数値で測るための指標です。
「工数が削減できたか?」「操作ミスが減ったか?」「顧客対応の平均時間」など、実際の業務に直結する項目で設定しましょう。
注意すべきは、KPIは“現場実感”と一致していなければ意味がないということです。
あくまで利用者目線の指標を設計し、改善の一手を講じやすくすることが大切です。
定期的に振り返りを入れながら更新していきましょう。
7-3.定着・改善サイクルの構築
DXは完了ではなく「継続」がキーワードです。
導入後も定着しているか、予定通りの効果が出ているかを確認し、必要に応じて改善を加えましょう。
PDCA(プラン・ドゥ・チェック・アクト)の考え方に沿った運用サイクルによって、DXは社内に根付いていきます。
特に、ユーザーのフィードバックを活かす仕組み、たとえば「システム利用者アンケート」や「現場からの改善提案募集」などを活用し、自社に合った改善文化を育てることが最終的な成功を後押しします。
8. DX定着と継続的改善のポイント
導入したツールを使い続けられるかどうか、そして継続的に改善し続けられるかが、DX推進の成果を大きく左右します。
このセクションでは、属人的な運用に戻ってしまわないための定着ポイントと、日々改善を進めるポイントを解説します。
8-1.利用者視点での運用設計
どれほど優れたシステムでも、活用するのは人間です。
現場スタッフにとって「わかりにくい」「面倒くさい」仕組みでは、浸透せず利用されなくなってしまいます。
だからこそ、操作画面や手順、導入目的の説明まで、すべてを「利用する人の視点」に合わせて設計し直す必要があります。
UI(ユーザーインターフェース)やワークフローの設計にも現場からの意見を反映させ、改善の余地があれば柔軟に調整しましょう。
8-2.社内教育・意識改革の実施
技術導入だけで終わらせず、組織としてのマインドセット(考え方や価値観)を整えることがDX定着の土台となります。
具体的には、新ツールの操作研修、課題改善のためのワークショップ、成功事例の社内勉強会などを継続的に実施することがおすすめです。
「変化を受け入れる雰囲気」を育てることで、トップダウンではない“自発的なDX”文化を築くことができます。
8-3.継続的なPDCAサイクル運用
一度導入した内容を放置してしまう企業は、DXに「成功したがその後失敗した」パターンに陥る危険があります。
定期的なデータ分析・ユーザーアンケート・業務改善会議などを通じて、常に小さな見直しを回す仕組みが必要です。
このようなPDCAのサイクルを習慣づけ、改善された部分や成果は社内でも見える形で共有しましょう。
使って終わりではない、運用して育てるという意識こそが、真のDX成功を支えます。
業務効率化のためにDXを導入するには、単なるツールの導入だけでなく、現場の課題把握・適切なプロセス設計・定着までを見据えた戦略が欠かせません。
自社に合ったステップで段階的に取り組むことで、継続的な業務改善と生産性向上を実現することができます。

 dx
dx